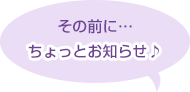地域別エントリー状況
マウスオーバーすると値を確認できます
タップすると数値を確認できます
| 団体所在地 | 応募数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 40 | 68.97% | |
| 愛知県 | 4 | 6.90% | |
| 福岡県 | 3 | 5.17% | |
| 北海道 | 2 | 3.45% | |
| 神奈川県 | 2 | 3.45% | |
| 大阪府 | 2 | 3.45% | |
| 埼玉県 | 1 | 1.72% | |
| 京都府 | 1 | 1.72% | |
| 兵庫県 | 1 | 1.72% | |
| 広島県 | 1 | 1.72% | |
| 愛媛県 | 1 | 1.72% | |
| 計58団体 |
審査のポイント
審査員がそれぞれに10作品を推薦し、1作品につき1票ずつ票を投じました。票の入った作品について約3時間30分に渡って議論を重ね、10作品を決定しました。
※今年の≪審査のポイント≫には選考結果についての具体的な言及があります。ご了承の上、お読みください。
審査のポイントに先んじて、今年の応募概要における主な特徴を改めて共有させていただきます。
- 昨年に引き続きグランプリ作品の再演義務がなくなったこと
- 賞金が例年通り【グランプリ団体に100万円贈呈】に戻されたこと
以上2点の変更点と従来の規定や方針を踏まえ、第一審査を行いました。
審査で推薦する10団体を決めるにあたって私が重視したのは、その応募文章に団体のこれまでの活動、現在地、これからの展望の3点が明確に書かれているか、そしてそれらが齟齬なく連動しているかどうか、という点でした。
「団体紹介」においては経歴のみではなく、経緯としてどんな活動を重ねてこられたが分かるかを、「公演の意気込み」においては作品紹介にとどまらず、これまでを経てなぜその作品を今上演するのかを、そして、「将来のビジョン」においてはその二点を踏まえての展望が見据えられているかを重視しました。
また、グランプリ団体に100万円を贈呈することと、それが再演支援という意味付けではないことから、活動に継続性や発展性が感じられるかどうかも判断の一つとさせていただきました。何を以てその高低を測るかについては非常に難しい部分でもあるのですが、書類審査であることを鑑みた上で、私個人としては具体例や具体案が添えられている文章に加点をする方針で進めさせていただきました。(例えば、社会との接続や劇場や演劇におけるアクセシビリティ向上をビジョンに書かれている場合は、そのためにどんな風に活動を展開していきたいか、どんな企画を予定しているかなどの詳細が添えられているかを重視しました)
団体の個性や強み、歩みや展望をしっかりと綴って下さった団体が多かったこともあり、最初に推薦する10団体を絞るまでにも非常に苦戦をしたのですが、以上を踏まえて、より具体的に過去・現在・未来における団体の在り方を文章で表現している団体を推薦する方針で決めさせていただきました。
そこから審査員5名による議論によって、互いが推薦した団体への意見交換やCoRich舞台芸術まつり!が掲げる指針に基づき、審査を進めました。地域、年齢層、団体形式、ジェンダーバランスなどを鑑みつつ、また、CoRichの特色であるアクセス数やクチコミなどの観客からの反応も把握しつつ、同時に、接戦となった時にはそれらの理由だけでこぼれてしまう団体が出ないよう、あくまで応募文章に立ち返る形で審査を進めることを心がけました。審査員がそれぞれ演劇業界で活動していることから、各々過去作品を観劇したことのある団体もあったのですが、それらの個人的な感触が審査に影響しないよう、あくまで「ここに書かれていること」を審査ガイドラインに据えることを努めました。
これも例年のことなのですが、各審査員が過去に仕事で携わった団体や知人が所属・出演する団体があることもあり、その点において私情の介入や不公平が生じないよう予めその背景を共有するという前提も踏みました。同時に、そのことによって、特定の団体を排するということが起こらないようにも細心の注意を払い、特定の審査員が持っている特定の情報や感触によって特定の団体が優位または劣位に働くことは決してないよう審査が進められた、ということもここに明言しておきたいと思います。
私が最初に推薦投票した団体とその理由の全てをここで明らかにすることは控えさせていただきますが、最終選出の10団体においては、最初の推薦投票段階で劇団UZ、コトリ会議が半数以上の票を獲得していました。また、私個人においては、世界劇団、ムシラセ、優しい劇団に最初の推薦投票から票を投じさせていただきました。また、惜しくも最終に残らなかった団体の中にも私が期待を寄せ、票を投じた団体が5団体以上あったこと、他にも議論に持ち上がった団体が多数に昇ったことも併せてお伝えさせていただきます。
なるべく透明度高くお伝えしたいという思いから長々となってしまったのですが、以上を踏まえ、最終選出団体を決定させていただきました。選出結果に問わず、それぞれの団体がその在り方や舞台芸術への想いを綴って下さった文章からは今年も多くの気づきをいただきました。今回の応募をきっかけに「観てみたい」と感じる初見の団体も多く、選出の10団体はもちろん、この春もできるだけ多く劇場に足を運べたらと思っています。重ね重ねになりますが、この度はたくさんのご応募ありがとうございました。観客の方におかれましても、是非クチコミなどでCoRich舞台芸術まつり!2025春にご参加いただけますと幸いです。
選出にあたって、事前に公開されている審査基準にあるように、応募テキスト・CoRichの情報・団体からの個別発信を総合的に見ます。そのうち応募テキストにおいては、「団体紹介」「本公演の意気込み」「将来のビジョン」が具体的か、その3つそれぞれと公に出されている情報に齟齬がないかを重視しました。今年はとくに応募テキストのクオリティが高かったです。だからこそ、自分たちの個性と魅力が自身の言葉でつづられているかは強いアピールポイントとなりました。また、オープンにテキストが公開され、『クチコミ』が重要かつ特徴でもある「CoRich舞台芸術まつり!」において、観客という存在をどう考えているかも注目しました。いずれの団体も違った魅力がありたいへん迷いましたが、これらをふまえて、審査会には次点をふくむ12団体を有力候補としてのぞみました。
審査会は想定していた時間を大幅にすぎても、妥協することなくさまざまな観点からの議論が試みられました。審査員それぞれの視点や価値観が同じではなく、各審査員がそれぞれ「なにをなぜ重要視すべきか」ということを根拠を交換しながら繰り返し話し合う、誠実な審査の場でした。
過程では、何度も『「CoRich舞台芸術まつり!」とは何か』に立ち返ることがありました。その際には審査員それぞれが「今、この時」におこなわれる舞台芸術フェスティバルとはなにかをあらためて考え、舞台芸術に思いを寄せる一人として背筋が伸びる思いです。
選出された10団体をふくむ応募団体58組、また同期間の今春に本番を迎えるほかさまざまな団体の存在を心強く感じながら、このフェスティバルが創作者・観客ともに充実したものとなることを心より願っています。
○重視した点
今回、私が最も重視したのは「応募にあたって、自分たちの言葉を見つけられているか」という点でした。応募にあたって「団体紹介」「応募公演の意気込み」「将来のビジョン」と一定量の文章を書かねばならないわけですが、この作業の中で、創作を振り返り、実際の上演やそれに対する批評をつぶさに観察し、手垢のついた表現ではない自分たちの言葉を見つけていくという過程に腹を決めて取り組んでいるのか。舞台芸術はチーム戦の総合芸術なので、この「言葉を見つける」という行為は、座組内また鑑賞者、ひいては社会との間の相互行為です。共通言語をゼロから立ち上げる、その相互行為に対して挑戦的で前向きな姿勢で取り組んでいるか、またそれが成立しているかどうかを見たいという思いがありました。その点が、CoRichがシステムで支援するクチコミの力を存分に借りて、表現の道を遠くまで歩んでいける条件だと考えたからでした。
○審査を経験して
審査の過程はダイナミックかつ慎重でした。審査員が選ぶ10組の団体には多く票が入る団体もあれば、1人しか票が入らないながら次点を多く獲得し議論の俎上に上がってくる団体もありました。迷ったら全員で丁寧に応募文章を再度読み込み、これまでの応募歴やCoRichでのクチコミも参考にしながら議論を進めました。審査では、実際の団体の選出と審査員同士の価値観のすり合わせが同時に行われました。例えば、地域性の高い団体の活動において何を評価するのか(作品の強度・おもしろさ?継続性?包括性?)、ジェンダーバランスは適切か(何をもって性別を判断する?女性作家への積極的格差是正措置を取り入れるべき?)について、審査員同士が理解を諦めて多数決にするのではなく最後まで対話による納得の上に議論が進められるよう、心理的安全を確保した上で、慎重な話し合いがなされました。予定時間を延長しても(!)対話を諦めない、この議論の姿勢にとても励まされる思いでした。これから10作品の鑑賞体験を共有する関係性として、その基本姿勢を確かめ合う場でもありました。
今回は総じて応募書類の質が高く、第一次審査で推薦する10団体の選出に大変苦労した。各団体が創意工夫を凝らした内容であることに加えSNS発信や動画配信、アウトリーチ活動や地域に根ざした活動など、公演内容以外に目を配る応募が多かったからである。ただし昨年同様にダンスなど身体表現の公演が少なかったことは残念に思う。加えて、これまでと比べ、第一次審査の時点で「観たい! クチコミ」がそこまで積極的に活用されていなかった点が気になった。応募歴のある団体は過去の応募内容からどれだけの進展があるかという点に着目した。最終的には「応募公演への意気込み」と「将来のビジョン」が具体的で説得力がある団体により高い評価をつけることになった。応募内容が抽象的なものや過去の応募と類似した内容のもの、字数を大幅に超過したものなどは推薦しなかった。
第一次審査で審査員全員の票を集めた応募はなかったため、1票以上を集めた応募をそれぞれ精査していく作業を続けていった。討議の過程で公演そのものへの期待や将来のビジョンの明確さに加え、団体のハラスメントやジェンダーバランスへの配慮が話題にあがった。賞味4時間にわたる議論のなかでは、上演地域や主宰・作・演出の男女比、年齢バランスについて他審査員からの意見を参考にして慎重に審査を進めた。
最終審査に進む10団体が無事に上演を遂げ、滞りなく催事が進むことを切に願っている。
もちろん第一は応募文書によるものであることは前提条件に、その上で決定を行わなければならない僅かな差の判断をどこに置くべきか。実際に審査結果をみる多くの皆さんをどこまで意識するべきか。これまである意味で原理主義的に行ってきた審査を、その結果の先にある受取手へのメッセージについて、これまでより意識された審査であったと思います。審査においても様々な試みを重ねながら、少しでも良い結果となるように努めて行く意思の現れと有意義に感じました。
最後に、ご応募頂いたすべてのアーティスト及び団体に感謝申し上げます。通過団体に限らず、今年も多くの皆様の取り組みを知ることが出来ました。それぞれの活動に敬意を表すると共に、一つでも多くの作品と出会えることを今後楽しみにしております。
※公演初日順。


ハッピーケーキ・イン・ザ・スカイ
あまい洋々(東京都)
★審査員より(曽根千智)
2019年に旗揚げしたあまい洋々。主宰の結城真央さんは、作・演出・出演・舞台美術・宣伝美術と多くの役をひとりで担いながら、一貫した劇世界を作り出そうとしています。作家自身の経験をもとに作品を立ち上げる際に生じる「当事者性の暴力」という問題を、勇気と優しさを両手に持って見つめる姿勢にエールを送ります。審査員の中でも「気になる」との声が多く聞かれました。かわいらしいケーキを糖衣として我々が劇場で何を目撃することになるのか、鑑賞者としての静かな覚悟を携えて開幕を待っています。


おかえりなさせませんなさい
コトリ会議(兵庫県)
★審査員より(松岡大貴)
昨年の準グランプリ団体であり、さらに岸田國士戯曲賞最終候補になっている本作を残すべきかは議論があった。それはネガティブなものではなく、もはやコトリ会議は何かを確立しつつあるのではないかという、我々の応援は必要なのだろうかという、ある種の信頼によるものであったと思います。しかしそれ以上の魅力によりCoRich舞台芸術まつり!においても最終候補に残ることとなりました。応募文章(本年度「CoRich舞台芸術まつり!」最初の応募者です)、地域性、過去の評価といずれも隙のない、コトリ会議が今年もやってきます。

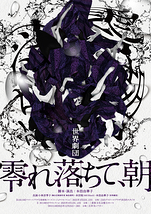
零れ落ちて、朝
世界劇団(広島県)
★審査員より(丘田ミイ子)
現役医師・本坊由華子さんがプロデュースを手がける世界劇団の拠点は「日本」。応募文章には団体の個性と強み、本公演で成し遂げたいこと、そして、劇団名に違わず「世界」を視野に入れたビジョンが脈々と綴られていました。土地を越えて人を繋ぐ。そのアクティブかつオリジナリティ溢れる活動を一層強化するべく上演されるのが、代表作『零れ落ちて、朝』の再演。2023年に国内5都市、今回さらに3都市でツアー上演され、より多くの人との繋がりが築かれます。医学界の世相から歴史の闇を切々と立ち上げるフィジカルシアターによって「日本」の舞台芸術が「世界」へと拡がっていくこと。そんな未知なる風景の目撃に期待を寄せています。


wowの熱
南極(東京都)
★審査員より(松岡大貴)
2年連続、南極ゴジラの登場である。昨年王子小劇場で観ていた団体が、今年新宿シアタートップスで公演をする。この驚きとロマンを共有出来る皆さんは長年の小劇場ファンでしょう。南極ゴジラの応募文章、WEBや発信する各種コンテンツはいつもワクワクさせてくれます。何か面白いことが起きるのではないか、すごいものが観られるのではないか、大きなうねりを作り出そうとしていることが感じられるからかもしれません。今回も『「創造」と「熱」をテーマに過去に類を見ない超常的な演劇を上演する。』と仰っています。今から楽しみにしています。


悲円 -pi-yen-
ぺぺぺの会(東京都)
★審査員より(曽根千智)
「ぺ」のヒトビトの集まりであるぺペペの会。応募文章からも、チケット購入から鑑賞後のつながりまで一連の制作の設計アイディアそのものが演劇という表現なのだという強い意志を感じました。「新NISA批評演劇」と銘打たれた本作品は、アートから資本主義への抵抗にも歩み寄りにも見えます。作品を観るために集うこと自体が人間の経済活動であることを反映して、日経平均株価がチケットの値段になっている点も面白い。分断が加速する現在社会の中で、集い方を考え続けるぺぺぺの会の果たす力強い問題提起に期待しています。


なんかの味
ムシラセ(東京都)
★審査員より(丘田ミイ子)
結成17年目となるムシラセは保坂萌さんが主宰する演劇プロデュースユニット。限りある文字数の中でも、参加する俳優への敬愛や観客に対する想い、演劇を通じてどんな社会に近づけたいかという願いがぎゅっと込められた文章がとても印象的でした。最新作『なんかの味』は、日本を代表する映画監督・小津安二郎の『秋刀魚の味』の再解釈に挑む、という意欲作。昭和の家族風景を活写した小津映画と現代の家族の在り方がどう繋がり、また派生していくのか。人と人がともに生きていく上での痛みと希望、それらの心の機微を掬い上げるその劇作によって、どんな瞬間と風景が劇場に立ち上がるのかを是非この目で見届けたいと思います。


kaguya
まぼろしのくに(東京都)
★審査員より(深沢祐一)
「幻のような劇」をテーマに福地海斗さんが2019年に旗揚げした劇団です。『竹取物語』を下敷きに現代日本を描く本作は、劇団発足当初から一貫している幻想的な作風に時事的な話題が織り込まれるようです。舞台芸術を含む文化芸術の存在意義を深く掘り下げ、日本を拠点に世界に発信しようとする意欲に満ちた「将来のビジョン」が審査会で話題にあがりました。「祭りと祈りの演劇の発信」を標榜するこの団体と「CoRich舞台芸術まつり!」がどのような化学変化を起こすか、いまから目が離せません。

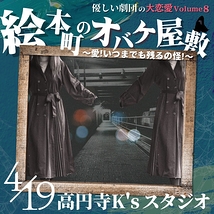
絵本町のオバケ屋敷 〜愛!いつまでも残るの怪!〜
優しい劇団(愛知県)
★審査員より(河野桃子)
2018年に名古屋で旗揚げした優しい劇団は、劇場にとどまらず多摩川の河川敷や名古屋の公園など様々な場所で野外劇も上演しています。掲げる「名古屋から小劇場ムーブメントをおこしたい」という言葉について、応募文では名古屋という土地柄に言及しながら、自身の言葉で足元の実感が伝わるテキストを寄せられていました。
今回の公演は、2024年から行っている、1日で顔合わせから稽古・本番を行う演劇企画の上演です。1日だけの演劇の作り方について創作過程だけでなく目標や根拠などが具体的に説明され、企画の魅力を具体的に伝えられていました。演劇の魅力のひとつでもある「生」の手触りを感じる姿勢には好感が持て、期待が高まります。

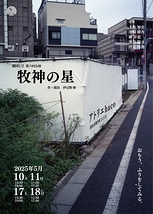
牧神の星
劇団UZ(愛媛県)
★審査員より(深沢祐一)
新型コロナウイルスが流行していた2020年、愛媛県松山市の小劇場「シアターねこ」を応援する目的で俳優の上松知史さん、座付き作家の伊豆野眸さんらが設立した劇団です。2024年に同劇場が閉館したあとも、地域に根ざした活動を続けています。劇団の稽古場であるアトリエhacoの柿落とし公演となる本作は、終戦時に実際に起きた事件を描いた作品に取り組む俳優たちの葛藤から、文化や表現の役割について考えを促す意欲作です。新たな創作拠点のお披露目となる本公演から、さらなる飛躍が期待されます。


湿ったインテリア
ウンゲツィーファ(東京都)
★審査員より(河野桃子)
その作風は「ネオ会話劇」と標ぼうされており、北海道戯曲賞で大賞や優秀賞を受賞するなど戯曲への評価も高く得られています。空間づくりや演出などの緻密な作品は、リアリティのある日常から、意識的あるいは無意識の層へといつしかもぐりこみ、また行き来するような不思議な感覚を、演劇という表現によって実現しています。
これまでアートスペースやギャラリーなどの小規模な場所を中心に公演されていましたが、今後、客席規模を拡大していきたいとのこと。応募文ではそこに向かうための具体的な数値目標も書かれていました。2024年に活動10周年を迎え、この先の新たな一歩になるだろう今回公演の上演が待ち遠しいです。
以上の10作品です!
次の最終審査では、審査員が実際に公演を見に行きます。
CoRichメンバーもクチコミをして
全国の舞台芸術ファンみんなで盛り上がろう!
あと一歩だった作品
最後まで候補に残っていた、大変惜しかった作品です。
“審査員注目の作品”として公表させていただきます。※初日順
| いいから早く助けてく | 匿名劇壇(大阪府) |
| Blue Light Tokyo | 劇団Tomorrow(東京都) |
| 逆光が聞こえる | かるがも団地(東京都) |