tottoryの観てきた!クチコミ一覧

海の五線譜
青☆組
アトリエ春風舎(東京都)
2015/12/05 (土) ~ 2015/12/14 (月)公演終了
満足度★★★★★
「固有である」ということ
アトリエ春風舎の空間に申し分なくはまった・・というより使いこなした舞台。黒光りする古い木板の床や、少なく不便な出入りルート、そして空間のサイズそのものも「虚構空間」へと動員して、普段は頭から離れにくい「春風舎で見ている」感覚を、忘れるほど完成度は高かった。
多言を弄しても掴まえる事の出来ない美、瑞々しさ、もう一つ(いや沢山)去来させるドラマ上の「何か」には、ただただ作り手の充実した創造の仕事がしのばれる事よ、と返すのが精一杯である。
終演後、階段を上った出口にややご高齢の夫婦が居て、見送りに出た役者二人程に嘆息を漏らしていた。ふだん劇場に行きつけている様子でない、何がしか縁故あって時々芝居を見に重い腰を上げてやってくる、そんなタイプ(勝手な推量だが)に見えたその女性は何度も「よかった、よかった」・・と、幾ら言っても言い足りないとばかりに繰り返していた。一足先に劇場を出た後、その夫婦と私以外客がなかなか出てこない。「そうだやはり台本を買っておこう」と階下に下りて購入。チラと見ると多くが客席に座ったまま、舞台のほうを見ていたりアンケートを書いている。
この光景が全てを物語ってるナ・・と良い気持ちになって劇場を離れたものであった。
青☆組観劇は多分3度目くらい。存在は随分前に知っていたが、チラシの体裁等からイメージしていたのは「女の子らしい可愛い日常を描く小品」。ところが意外に骨太な構成をもつドラマを書く。 特徴は「過去のある時代」の風景を、往時をしのばせる「嗅覚」に訴えるような風俗をうまく取り込んで、世界を再現、再構築する。青☆組の舞台の重要なポイントだろうと思う。
過去へと遡り、「その時代」でしか起こりえないディテイルを組み込んだドラマが展開する。この「時代性」のこだわりは、話じたいはフィクションだが「確かにこういう時代があった」、という事実のほうに重きが置かれているということである。 その時代にも人々は健気に、懸命に生きていた、その証であるそれらの風俗が、逆に現在を照らしてくる。 様々な「変化」を疑わず(携帯電話の普及が如実)、次々と過去へ置き去られていく、この「変化」への鈍感さ(適応のよさ?)は実のところ、「支配する側」には大変都合のよろしい性質に違いない・・・とそんな事も思う。
今回の芝居、隙やほころびが殆ど見られない完成度をみた。もっとも、本当に良い作品に「完成」という言葉は使いたくないものだが、敢えて使うなら、この「完成」に対し、ひねた私はまず困惑するのである。
演劇という芸術が「完成」をめざす営為であるのは当たり前なこと。だが、皮肉なことに「良い終わり方」で気持ちよくなる分、考えない。それでよいのか、と考えてしまう。
今作も、「気持ちよく」終わる。感動がひたひたと来る。「海の五線譜」に感動したのならその所以は何か、私としては掘り返すべきなのだが、ただ感動の後味のまま、寝かせておきたい心情がある。
しかしそれでは×だと、自分の声が言うので少し書いてみる。 ・・劇中のエピソードは決してありきたりではない、珍しいと言えるだろう、ただし誰しもこの程度の逸話は持っているものかも知れない、と言う程度のものでもある。 絶妙に独自性のあるお話を通して、この芝居は人生、愛、世代の継承、自分自身とは何かについて、問いを静かに投げかけている。
この台詞に無い「問い」が可能であるのは、優れて「固有」な、確かに「そこにあった」お話としてリアルに再現されているからだ。
しかし同時に、「固有」なものとして現前しているほど、一回性の生の儚さが息を吹き込まれた人形のように存在してしまっている。これはもう儚み、いとおしむしか手の出しようがない。
かくして、この物語の登場人物---皆が皆切実な生を生きている---の輝きや「存在」感は、手の内におかれた命のようにそっと胸にしまいこむしか、やはりないのだ。 謙虚にそのことを認め、作者、そして俳優諸兄にありがとうを言いたい。
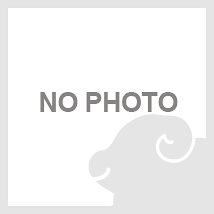
ピアノと物語『アメリカン・ラプソディ』『ジョルジュ』
座・高円寺
座・高円寺1(東京都)
2015/12/18 (金) ~ 2015/12/20 (日)公演終了
満足度★★★★
評伝と音楽(「アメリカン・ラプソディ」)
ピアノ生演奏付の朗読舞台「ジョルジュ」と「アメリカンラプソディ」のうち前者は前に観ていて、後者を観た。 作者斎藤憐(れん)は劇作家の御大といった所で、硬い文体(台詞)のイメージが強かった(人間はそうでなかったようだが)が、ガーシュウィンの音楽の人間臭さ、猥雑さゆえか(彼はジャズの元祖とされている)、ぐぐっと迫ってきた。エピソードを時にユーモアをまじえて紹介し、硬いというより丁寧な文体は誠実で、ガーシュウィンの人生とその仕事に体するリスペクト(愛)がそれを説明するまでもない感じで伝わってくる。
「語り手」として書簡を交わしあうのは、ガーシュウィンと縁のあった男女だが、それぞれ彼の人生にそれなりに噛んで居り、単なる紹介者でなく、次第に彼と彼を取り巻く人達との関係、時代との位置関係が像として立ち上がってきて、最後は作家の逆転勝利。即ち、演劇的感動が実現する。(感動の度合いの点では自分がジャズに傾倒していた事が大きいかも知れない)
中央のグランドピアノには佐藤允彦がつき、それを挟むように上手にケイ(女性)、下手にヤッシャ(男性)が立つ。女性は声楽家の土居裕子が演じ美声(歌)を披露するが、演技も意外に深い所に達していた。男性は低い美声を持つ俳優座の斉藤淳(歌は披露しないが)。
この「劇」の主役は、その生音が披露される「楽曲」である。それがまた彼の実人生という背景の前で、生き生きと立ち上がる。よく知られた「ラプソディー・イン・ブルー」は中でも大曲で、ジャズピアニスト(の中でも「楽譜を見て弾ける」基礎の出来た知性派の印象があった)佐藤允彦の演奏を通して、これが作曲者本人によって披露された1920年代当時の人々の驚きが想像させられ、唸った。同モチーフを繰り返しながら即興的に発展して行く形態は、ジャズそのものと言えるが、発展形のバリエーションの幅が大きく、構成に意図が感じられるので、即興演奏「的」ではあるが完成度の高い一つの楽曲である。
ヨーロッパからの輸入でない、アメリカ独自の音楽を生み出したと評されたこの音楽家はロシア系ユダヤ人の移民の息子。黒人音楽から発展したジャズの要素を取入れて楽曲を作った彼自身は白人だが、小さい頃は喧嘩ばかりして育ち、ピアノに出会ったのは14歳という。急激に入れ込み、15歳の時にはピアノ弾きとしてお金を稼ぎ始めている。クラシック畑の評論家からは絶えず酷評を受け続けたが、大衆からの人気に押されてピアノ楽曲を書き、カーネギーの舞台も踏んだ。ブロードウェイへ楽曲を提供して興業的な失敗も経験するが、その一方で彼は自らの音楽家としての課題=オペラ楽曲(だったか、交響的な本格的楽曲)に取り組むため、管弦楽器の作曲法を学び直したりしている(一度ラベル、いやリストだったか‥に申し込んだが「天才に教える事はない」と断られている)。音楽というtoolを天から授けられ、それと共に爆走したガーシュウィンは多くの浮き名も流しながら、39歳の若さで天に召された。
ジャズに入れ込んだ者としては、ガーシュウィンという存在はジャズ史では上代の領域の人。常に発展進化する宿命を課されたジャズは現在進行形での「変化」に躍動するものでもある。ゆえに過去作品に遡るのもせいぜいビバップ止りであった。だが今回の「音楽」の物語は当時の躍動する「変化」の場面に立ち会わせてくれた。ジャズへと繋がる瑞々しい萌芽、であると同時にそれ自身として輝く作品がそこにあった。

紛争地域から生まれた演劇シリーズ7
公益社団法人 国際演劇協会 日本センター
東京芸術劇場アトリエウエスト(東京都)
2015/12/16 (水) ~ 2015/12/20 (日)公演終了
満足度★★★★
「物語」の普遍性
今年7回目、毎年観るなど、況や全作品観る事など到底無理(時期的にも)だが本当は観たい・知りたい・参加したい企画だ。 「第三世界」という言葉はまだ有用であるのか知らないが、その演劇に触れるのは貴重。厳しい状況は演劇の価値を試される試験場のようにも思える。
三演目の内、フィリピン作家作品を観劇した。音楽劇だという。それで、リーディングにもかかわらず鳴り物・楽器を使った贅沢な出し物になっている。役者に加えて音楽担当もおり、端のほうで演奏する。役者も全員道具や楽器を使う。演出は黒テント出身、立山ひろみ。 リーディングという「分野」の可能性の点でも、興味深い演目。
作品が取り上げているのはミンダナオを拠点とするモロ民族解放戦線とフィリピン政府との対立(紛争)問題である。 最近はこの問題を知らない若い人が増えているので、子供にわかる劇を、との注文を受け、作ったものだという。父母を失った兄妹と仲間が旅をし、やがて散り散りになり兄妹も分かれてしまう。そして兄はある土地のギャングに取り込まれ・・ 妹との不幸な再会、だが困難の中、勇気ある選択へ・・・「子供」目線で見れ、大人の鑑賞にも堪えるドラマだった。音、音楽の使い方も良い(出演者の一人が時々自動とあり、音楽担当もそうかと思えば所属が記されてなく、不明。ただ、それっぽい雰囲気。良い意味で脱力させてくれる音楽は私たちの皮膚から入り込むように心地よい。)
戯曲を発注したのはPETA(フィリピン教育演劇協会)、かの地では住人の意識啓発や自立のための演劇を用いての活動が広く根気よく続けられており、70年代からPETAと交流のある黒テントを通じて今回紹介されるに至ったという。
お話にはイスラム教(モロ)と多数派のキリスト教の対立が描かれている。そうした対立がなく共存状態にあった村に育った兄妹は、それぞれキリスト教とイスラム教と宗旨が違っても普通に過ごしていた。ところがあるとき二人の何気ない会話の中の「イスラム」という言葉を、ある平均的なキリスト者の家庭(集団?)が耳にしただけで警戒し、さげすみ、排除する、という場面がある。
この対立を利用・助長する勢力(はっきり言えば体制側)に同調するキリスト教マジョリティの存在が、ここ日本の、ある局面での自分と重なって来たりする。鋭くて痛い場面だった。
優しく人間的なこの1時間のお話は最後まで「問い」を発しながら終わる。 観客に「あなたはどうしますか」と問いかけるが、(当然?)反応はなく、「そうか、今、考え中なんだ」と言う。「考え中」・・この語が何度もり返し発される。
お説教でなくエンタテインメントでありながら、「問題」をしっかり刻みつけるお芝居、一つの判りやすい見本のように思われたが、「子供たち」と言えば、今の日本はどんな状況だろうか。
正しいと信じることを大人も言えない時代の、子供の「知る」環境の劣化は考えたくもないが現実なのだろう。
・・・・今は言いづらいが時が経てば言える時が来る、<今は忍耐の時>。だがその<今>は延長・更新され、「喋らない」我慢もいつしか追加注文され、受け入れてしまった日本人。 大人よりも、未来を担う「子供」への、演劇の可能性を探るのが今や正常な態度かも・・ともふと思う。さほど深く考えている訳でもないが、コトバにはしておこう。

高学歴娼婦と一行のボードレール
猫のホテル
こまばアゴラ劇場(東京都)
2015/12/10 (木) ~ 2015/12/17 (木)公演終了
満足度★★★
ある女性についての女性の筆による劇
実話を基に書かれた舞台だというが、その基の事実が説明されない事には評しようがない所があった。台詞の中にヒントは散らしてあったようだが。前半、劇団員男子のだべりの戯れは団員の長い付き合いそのまま舞台に乗った塩梅が自然で緩急もよい。見事。「事件」の被害女性をめぐる、やや下品た会話の、隠微な部分への「踏み込み」具合が絶妙である。一転、いつしか男が消え、女性二人による対話のシーンでは、事の本質(女性の存在のあり方=生き方)に迫るやり取りが展開するが、これが非常に抽象的で、「何か切実なものがあったのだ・・」とある結論らしきものを仄めかして去る、と行きたい所、そのために置いたヒントが、ボードレールの詩、しかしこれがあまりピンと来なかった(何と言ったかは忘れた)。 他の何かでも置き換わる抽象度の高い表現で、着地がいまいち、対話の内容も熱をこめて語るわりに、語る役者の口に馴染んでいないのではないかと勘ぐられるような具合だった。
言うなら「思想劇」。・・これは余程深く思考を潜らねばやれない代物という事だろうか。 それとも、女性被害者をめぐる劇の言葉は、女性からは共感を獲得できていたのだろうか・・。
ところでこの公演の趣向としてバーのママ役が日替わり(三名)で、おそらく出演者の参加事情からなのだろうが、私の観た回は平田敦子、体格さながら演技者としての骨太さを間近に堪能させてもらった。

宮地真緒主演 「モーツアルトとマリー・アントワネット」
劇団東京イボンヌ
スクエア荏原・ひらつかホール(東京都)
2015/12/08 (火) ~ 2015/12/10 (木)公演終了
満足度★★★★
演劇を建てるには音楽を犠牲にしなければならない、、のか。
東京イボンヌ初観劇。その期待を「観たい!」にも書いたが、舞台上にクオリティの高い演奏家を置き、芝居にもしっかりと噛む。如何にも贅沢な、未だ観ない光景だと思った。私の一方的な期待だが、舞台はそれとはやや違って、その違いは、この舞台を「演劇」として観る場合、大きかった。 「未だ観ない」とは括弧付きで、オケ付きの「舞台」としてはオペラがあった。こちらは得意分野では全くないが、ズバリ今回の舞台はオペラかオペレッタの崩しみたいだ、と思った。
モーツァルトが登場し、声楽家も居るので「フィガロの結婚」の一節が歌われてもおかしくないが、本格的な声楽家(欧州在住日本人の声楽家をわざわざ呼んだというから気合いは半端ではない)が、そこでフィガロを歌ってしまったら、そこはフィガロの空間以外の何者でもなく、それを包みこんで物語が流れるはずの「芝居」のほうは、こいつには到底勝てない。
全体にコメディの味付けが濃く、近世ヨーロッパの王道的傑物二人の懐の内に遊んでいるといった感じで、そうした細かな笑いを挿入することで傑物の傑物たる所を引き立てているとしても、以上にはならない。
ドラマとして見た時、超有名人であるアマデウス・モーツァルトとマリー・アントワネットが何ゆえ「特筆」されるべき人物であるのかを、作家独自の視点で「説明」し得ているか・・それが気になった。 一般教養のレベルで、少し勉強すれば判るだろう・・、という前提を受け入れるにしても、作家自身の捉え方は作品の中に一本なければならないように思う。
プロの声楽家にオペラの一節を歌わせること有りきで、その上で「演劇」を成立させるギリギリの努力をされたのだろう・・が、相対的に「演劇」が疎かになったとの評価は、否めないように思う。
そのポイントを幾つか羅列すれば・・
○構造としては「芝居」が始まり、その中に「音楽」が組み込まれる、という外形はとっているが、「フィガロ」の一場面が歌われると、その場面の位置づけがあやふやになる。「オペラが上演されている場面」なのか、「芝居の進行上の挿入歌」なのか、何らかの意味を付されねばならないが、この舞台では「ひらつかホール」で声楽家が声を披露している」という事になってしまう。もちろんその側面があってもよく、それで拍手が起きてもよいのだが、しっかり「演劇」の中に組み込まれているかが問題だ。
○他の演奏場面も、「上演・演奏風景」として位置づけられている事が多かったが、生演奏の再現力はドキュメント性を強く持ってしまい、一節の終わりまでしっかり演奏する事で尚更、音は独り立ちしてしまう。「上演・演奏風景」以上のものになる。つまり「ひらつかホール」で演奏を披露している、という事にやはりなってしまう。
○これには、(他の投稿にもあったが)「物語」の流れに沿った音楽であったかどうかが「音楽そのもの」から伝わって来ないという事が大きかったのではないか。有名な曲目をチョイスしたのだとすれば、そのチョイスの仕方が既に「音楽・演奏ありき」で「演劇」は二の次だったとなりそうだが、実のところどうだろうか・・。
○また、これを言っては身も蓋も無い?が、複数の声楽家を招いたことで一定の「披露の場面」を準備することとなり、歌の比重が大きくなった、その事で「物語に沿った音楽」という使用はいよいよ狭まり(オペラ曲では尚のこと)、モーツァルトの仕事の中でも歌劇が前面に出ることになった。その事がストーリーの組み立て(あるいはモーツァルトという人物の位置づけ)に与えた影響は無かっただろうか。。
○同様の難点は、舞台の上方に演奏者がデンと終幕まで座って、「演劇」の中に生きる存在として見えにくいという事もあった。(他の難点がなければさほど気にならなかったかも知れないが)
○モーツァルトの音楽が「民衆」に対して、本来寄り添おうとするものだったという視点、モーツァルトの中に庶民性を発見する事が、フランス革命をドラマに大きく取り込むことの意味になると思われるが、(でなければ例えば、逆に彼の中の貴族性が暴かれ、彼自身の=神との約束との=葛藤が浮かび上がる、といった展開も可能?) フランス革命に対し懐疑的な描き方がされており、はっきりして来ない憾みがある(能力のないリーダーが威張ってみる等のギャグ)。 ・・権力の肥大化、その挙句の絶対王政の下、硬直した社会システムに苦しむ人々、そしてついに暴動に至った、つまり、「不平分子」が居たり「洗脳」によっては、大規模な革命など起きない。革命の前に支配と権力があり、沈黙する民衆はその下で疲弊する。さてそこへアマデウスは自らの音楽で何を変えようとしたか。そして「何に挫折したのか」、そこを鋭く描いてもほしかった。
彼の音楽が受け入れられていく、人気を博していく、という導入は良いが、人気の中身が何であったかについても、知りたい所だった。
○マリーとの接点は、フィクションであって良いけれど、モーツァルトがどこに立っており、マリーとどう出会ったのか(人に理解されない穴を埋めあう、とか、政治的立場が違うにも関わらず惹かれあう、とか・・)、アマデウスの物語にとっての、マリーの存在の「意味」。
○神に頼んで地上に降りたモーツァルト、という着想は色んな可能性を孕んでいると思う。ただこの部分にしても、神世界に属する存在が「人間」になった時、初めて発見することというのがありはしないか。それとも今回は何度目かの事か。何のために彼は人間界に来ようとするのか、そのメリットは・・。そういったディテイルはとても大事だと思う。彼にとっての「超課題」は何か・・「演劇」ならそここそ重要だと考える。
難癖ばかりになってしまうが、舞台装置は見た感じからして辛いものがあった。横に長く、前後に狭い。中央で芝居をやると役者がはけるのに時間がかかったり。中央の(高台二つの切れ目の)通路はいまいち利用されていない(使いづらかったか)。上段に楽隊が占め、上手中央寄りにピアノも置かれ、動線の工夫も大変だっただろう。
(これらも「演奏を聞かせるパフォーマンス」の一つと見直せば、有効な形なのかも知れない)
様々な条件を制約と抱えながら舞台化を遂げた努力はしのばれ、「思い」のようなものは感じる、ものの、「演奏」を「演劇」(物語)の中に美しく組み込む試みは、まだその「始まり」に思えた。 難しい取り組みを、それでも取り組み続け、成果をあげて行って頂ければ私は嬉しい。
・・・と「演劇」(私定義による)好きの一人が長々と申したが、単に「違う路線」ゆえの「違い」に過ぎないかも・・

杏仁豆腐のココロ
海のサーカス
ザ・スズナリ(東京都)
2015/12/09 (水) ~ 2015/12/13 (日)公演終了
満足度★★★★
「アジアンスイーツ」と同じスズナリで鄭義信作のスイーツを。
何年か前の「アジアンスイーツ」(鶴田まゆ、清水宏二ほか二人出演)は金久美子のために書下ろした遺作(金にとっての)の再演だったが、今回の「杏仁豆腐」は13年前の初演で演じた佳梯かこ本人による、相手役を新たにしての二人芝居。やや年齢差が気になる(佳梯氏のほうが幾分年を重ねている分、夫婦関係の設定が限られてくる)。次第にそれはそれと見えて来るが、鄭演出の「笑いをおいての、涙」への急落効果を成立させる演技面の要求に、夫役・久ヶ沢徹が必死に応えようとはしているがその分だけ夫婦関係のあうん、距離感、濃密感が出なかった嫌いがあるんじゃないか・・という風に思った。どうにか成立していたし大きな拍手をもらって良い芝居だったと思うけれど・・。
ただ、後に明らかになる「不幸」(即ち別れの原因)を巡って、語る口が男の本音のありかを「それを口実に別れたいだけ」だとみる余地を与えていた(そう見えた)ので、これは狙いとは違うのではないかと想像する。後からそう思えて来てもそれはそれで良いが、その瞬間は本当の愛、愛ゆえに別れるという事が本当にあるならばその本当の愛が、肉感的に見えたかった。二人の(実年齢の)年の差は舞台上の夫婦関係にも影響していて、夫は最後には相手に強く出られない、という設定に見えなくなく、「愛ゆえに別れる」苦悩の深さを出すのは至難にみえた。
しかし鄭義信の戯曲には心をさっと刷毛でさらうような、清涼感がある。ドロドロした夫婦の物語であるのに。実は二人は結局別れないのではないか、とそんな風にも見えるのは、多分戯曲の狙いではないんだろうな・・。如何に二人らしく「別れる」のか・・そのために二人は今そこでの時間を過ごしている。そして、そこには間違いなく愛がある、そんな贅沢にドラマティックな状況は、そうない。
結論は、「愛」である。

緑子の部屋
鳥公園
こまばアゴラ劇場(東京都)
2015/11/27 (金) ~ 2015/12/07 (月)公演終了
満足度★★★★
迂遠の虜
ここにいない緑子と接点のあった二人の男女と兄による会話劇。ただし読み解くのは至難だ。目の前で展開する言葉のやりとりと行為は、しかし不思議と何らかの背景に裏付けられているように見える。
終盤、男の不可解な言動が始まり、女はそれに対して奇妙な対応をする。男の不可解さがポジで女の奇妙さがネガなのか、その逆なのか・・ 女のそれだろうと類推する。やはり女性目線で書かれた芝居であり、「男」は現象として現前し、女がどうふるまったか、が焦点化されているのだ。
簡素だが一定の具体性を持たせた装置と、十全な説明未満にとどめた台詞、注意していないと意識されないが場の空気を支える音響、全体にストイックな作りは好みである。
今回「素人」「プロ」について意識したという主宰の言であるが、素人性すなわちありのままの自分自身(の心?)だとすれば、今後の発展は作者の心の探求次第という事になるのだろうか・・。
今回再々演という事で、初演から関わる三名によるトークは興味深かった。色々なことを考え、独自な製作を行う西尾氏主宰の鳥公園の「発展」の形は予測しようもないが、ともあれ「発展」されんことを。

レミング―世界の涯まで連れてって―
パルコ・プロデュース
東京芸術劇場 プレイハウス(東京都)
2015/12/06 (日) ~ 2015/12/20 (日)公演終了
満足度★★★★★
感覚総動員で美味を味わう極上の・・。
一流とはこういうものか、と一つの理解に導かれもしたが、テキストは寺山、および松本雄吉+天野天街の奇妙奇天烈な言葉遊びの世界。連想ゲームや反復でこの雄大さは何なのだ・・と思う。とにかく気持ちがよい。俳優の声がすべて快く響く(声がよいのだ)。主役級の霧矢の歌がアテレコでないのにまず驚くし。柄本時生のくちゃらけたキャラはきっちりはまって溝端氏と対になっており、一々挙げないが周辺の役どころの一人一人が皆十全に妖艶さを放っている。妖艶さが充満した舞台(色っぽいシーンはほとんどないが)、という表現が今のところ最適だ。音楽は機材を使いギターは演奏。下手ステージ下で内橋氏の挙動が見てとれる。 美術がバトンを多用して場面転換をスムーズに行い、すばやく下りて来る速度も何かシステマチックな味を全体に与え、何よりどの部品も色彩とデザインが良い。照明もバシバシ、ガンガンやってる。音楽に戻れば、冒頭と最後でテーマ曲らしい音楽に合わせて俳優らが変則的に靴音を鳴らして動いたり、ねずみの話が出るとネズミの踊り(これは秀逸)をやるなど。どの要素も意味を持たされないものはない、と納得させる緻密さをみせながら、交わされる言葉の色彩の多様な変化も、全体のダイナミックな「変化」の一部を構成している。 つまり、ストーリーを導くために言葉が利用されているようではないんである。たまたま(自然現象のように?)吐かれた言葉の端をつかまえて、場面のほうがやってくる(そこは唐十郎にも通じる「アングラ的」テイストだろうか)。 とにかく装置、照明、音楽(音響)、俳優の動き、そしてコトバ。全てが拮抗しながら主張しながら舞台が進んでゆく。
これは維新派の世界なのか、原作が持つものか。・・松本氏演出舞台は「石のような水」で初めて観、左右の歩行のリズムが特徴と感じたが、全体に未消化、松本演出自身が「(松田正隆氏の)脚本がよく分からない」などと言っていた。松本氏にとってはこちらの方が「分かりやすい」のか・・・。
とまァそんな事も思い出しながら、ただただ快感だった舞台の周辺の落ち葉を拾うことくらいしか出来そうにない。

悲しみを聴く石
風姿花伝プロデュース
シアター風姿花伝(東京都)
2015/12/11 (金) ~ 2015/12/21 (月)公演終了
満足度★★★★
銃声の町、土壁の中の静けさ、心の炎
昨年の「ボビーフィッシャーはパサデナ・・」に続く、劇場支配人那須佐代子出演・上村聡史演出の海外作品。今回は同名小説の戯曲化である。昨年の舞台が圧倒的だっただけに今回はどうかと、不安と期待を交差させながら客席で開演を待つ。戯曲の出来という点では甲乙ついてしまうものの、深みのある舞台にまた出会えた喜びが勝った。 必然的に「静寂」をともなうこのドラマの劇的状況は、戸外で断続的に鳴り響く着弾音や銃声によってさらに強調されるが、ドラマ上の問い(観客にとっての不知)は、そこにずっと横たわっている男と、彼への女の語りかけによって純化する(答を追う価値を高める)。
女はどこか諦観を帯びているが、夫の不在(ある意味での)によって熱情を帯びてくる。それは希望にも繋がっている。虐げられた者がつかむ希望は普遍的であり、瑣末な凹凸をならし、背徳と地続きである。 自由の地平を切り開く者は、自分自身であろうとし人間であろうとするがゆえの背徳へ至るものなのではないか・・などと考える。キリストは当時の支配的考え方では背徳者だった。 このドラマの人物たちのあられもない秘部を、観客は最後には受け入れてしまう。舞台上で起こることが視覚的に、徐々に明瞭に現前させてゆく大胆な演出の賜物でもあるだろう。

あゆみ(長編)
野方スタジオ
野方スタジオ(東京都)
2015/11/19 (木) ~ 2015/11/25 (水)公演終了
満足度★★★★
初「あゆみ」。野方にて。
マンションの一室をスタジオとして運営しているこの場所で、先日シアターミラクル公演を終えたばかりのfeblabo作「あゆみ」を間近に観た。長方形のスペースを壁沿いに椅子で囲み、役者がハケる場所は客席の輪の中の椅子数個のみ。主人公あゆみの誕生からの一生の物語は、「歩む」形態をとりながら描かれ、客席の輪の内側を円状の道として進みながら、女優らが入れ替わり立ち替わり主人公や母、友達、同僚その他諸々を演じる。主人公の女の子も一人ではない、というのがミソだ。入れ替わりも潔く快い。膝の先30cm位を役者たちが横切ると風を感じるほどの接近具合で、時おり目が合うことも。観客数は「本日最多」との主宰の弁だが、狭い部屋の中、対面の客の顔もくっきり見え、他のお客はどう見ているんだろうとつい表情を覗いてしまう。・・そうした全てが新鮮で、面白かった。
舞台の出来としては、何より女優たちの好演が大きい。出ずっぱり、快活、しなやか、爽快だった。全員が同時に中央に立つ事はないが、椅子に座っている間も安閑とはできず、劇が流れる時間を呼吸し、スムーズにバトンして行く。全てを7人が総力で作り上げた舞台、爽快。
作品は、柴幸男らしい(といっても「わが星」位しか知らないが)、人生という「時間を俯瞰」する作品で、印象的なエピソードを織り込みながら進行する。展開がリズミカルで、そのリズムは終り近く、「山を登る」スローな歩行として、人生の道行きの比喩となる。歩行する彼女の「想念」に浮かぶシーンとして、それまで紹介されたエピソードの謎解き(後日談など)が簡明に点描される。この「進んで行く」感は、音楽のように響いてエピソードと併走する効果を持つ。うまい。
野方スタジオという小さな主体のプロデュースとして、この美しい演劇が生み出された事は、様々な可能性を開かせる話題だと思う。無から何かを生み出す「創造」の営為が、演劇である。
「あゆみ」という作品について。ここには「感動」の典型的なモデルがある(意味が重複しているが・・)。この点が考えさせどころなのだが、最初の投稿では雑な思考そのままを書いてしまった。書き改めたら、ネタバレに載せることにする。

ロボットの未来・改(またはつながらない星と星)
中野成樹+フランケンズ
アキバナビスペース(東京都)
2015/11/20 (金) ~ 2015/11/25 (水)公演終了
満足度★★★
ロボットと人間の境界
人間をその比較対象とする場合の「ロボット」とは、ロボット的存在・・即ち、明確な目的がありそのための行為(仕事)を行う存在のことで、人間がロボット的である局面を見出すことが目論見の一方。他方ではロボットが人間に近づき、「人間的」という尺度において精度を増したときの、ロボットの「人間的」あり方を見出す。時代を、既にそんなロボットが登場している未来に設定し、一見区別のつかないロボットと人間が共存している状況を、今の私たちの生活風景の延長として眺めてみる・・ そこがこの作品の狙いだろうかと思う。
このアプローチで多彩なシーンを連ねた「ロボット・人間エピソード集」となっており、精神科のカウンセリングに来る相談者と医師との対話など、興味深いシーンも幾つかあった。しかし、この着想が触手を伸ばし得るだけの幅は各エピソードに見られるのだが、一つ漠然とした印象を脱せなかったのはなぜか・・。 うまく言えないが「主語」が統一されていない感じ、とでも言おうか、見方を統一できない感じが残った。人間にとって切実な問題につながる警告というようなものになっている訳ではなく、面白がるならもっとやっちゃって良いのではないか、とも思う。あるいは、表現上の拙さの問題だろうか(俳優の)。
ロボット=人間論は面白いテーマだ。テキストの練り上げの余地があり、今後もバージョンを変えるなどで(断続的にでも、シリーズ化などして)温めていってほしい。

クリスマス解放戦線
渡辺源四郎商店
こまばアゴラ劇場(東京都)
2015/11/21 (土) ~ 2015/11/23 (月)公演終了
満足度★★★★
バブル風味の運動ソース、禁欲のカルト添え
設定が明快でスパイスが効いた現代風刺・近未来劇。現実離れもここまで行っちゃ・・と突っ込み入れるも一々人間(社会)のウィークポイントを穿ってるからその風刺に笑って見進めれば、最後にはしっかりとオチが。達つぁんの「クリスマスイブ」がプロテストソングとは、これ如何に。。あり得なくもない話に思えてしまっているのが、不思議である。

スポケーンの左手
シーエイティプロデュース
シアタートラム(東京都)
2015/11/14 (土) ~ 2015/11/29 (日)公演終了
満足度★★★★
作家はしてやったり。左手にまつわるお話。して舞台は。
小川絵梨子演出舞台を暫く観ていない・・という理由で奮発してチケットを買った。私が初めて小川演出を観たのは同じシアタートラムで上演された「クリプトグラム」だったか、イキウメの芝居だったか・・前者では誠実な印象を受け、また新国立「OPUS/作品」もまず楽器の扱いがgood!、脚本共々よく出来た舞台だった。他の二作程がいまいちと感じた、その原因を今思い出す・・・なるほど。
それは、小川氏が取り上げた作品を、演出家としてスマートにスタイリッシュに形にする、試みや技術を見せられている感触が強く残り、演出家が作品そのものをどう捉え、作家がはき出そうとしている何かを、どう咀嚼して自らも提示しようとしているかという部分、演出という仕事についての議論になって来るだろうけれど、私としてはそこが見えないのは不満、そしてそれは脚本のせいではなく演出が踏み込んでいないからではないか・・と感じたのがその中身だ。
今回の上演にそれが当てはまるのかは判らないが、トラムでの一時間半弱の芝居が終わったとき、どうやら作者はこのあたりを狙っていたのだろう・・と、本上演とは異なる形を想像して補い、それで漸く納得して劇場を出られたという事があった。
このお話は、様々な解釈の余地があって面白い。鍵となるのは中嶋しゅう演じる左手の無い初老の男、彼は十代の頃同年代の悪い連中によって、山あいを通る線路に左腕を押しつけられ、列車にひかれた。そしてはね飛ばされた手首は連中の一人が持ち、去り際に「さいなら」と手で挨拶し、持ち去ってしまった・・と、言う。以来彼は(それを始めたのが何時かは判らないが)その連中と、左手を探し続けている。・・そして物語は、彼が探しているという左手、本物でない左手を差し出して報酬を得ようとしたあるカップルが、目論見を見破られ、男は怒り心頭に発している所から始まる。
ドラマ構造としてはミステリーで、呻き声の聞こえる物置に向かって銃を撃ち込む衝撃なシーンから、そこに居る男と彼に関わる二人の背景が、徐々に明らかになる。
人物は三人の他、ホテル(そこはその一室)のフロント係(一癖ある男)の計四人。このフロント係はこの芝居の中では、左手の無い男を巡る話の本質からややズレた一人語りのシーンが長くあり、それは男に対して「死を恐れない」態度を取る事の真実味を与える背景とはなるが、語りの時間は独自で不思議な魅力を放つシーンとして成立している。・・それはともかく、謎解きがほぼ終えた「現在」、事態は「左手」を巡るやり取りにおいて、既に結論は出ていて、男は怒っているが二人を懲らしめて左手が出てくる訳ではない。そこで作者は男に過去や心情を語らせているのだ。
さて、終盤に決定的な「謎解き」のヒントを見たように観客が思う一瞬のシーンがある。男が何度も偽物をつかまされてきた、その数だけ彼のトランクの中に大量の左手(のミイラ)が入っており、手錠をはめられたカップルが男の不在中トランクを開けてその衝撃の物体たちを見る、というシーンの後、男が戻って来て部屋を撤収する際、ぶちまけられた手を拾ってトランクにしまうのだが、一つだけ残る(なぜ残すのかの説明が十分でないのでわざとらしいがそれはともかく)。そして二人が去って他者の視線の無い間に、男はその残った手を拾い、「おや?」と見直して、自分の右手と比べてみる。自分のものかも知れない、と思う。が、その考えを打ち消す・・という一連の動作だ。ここには、左手探しが彼の生き甲斐となっており、本当に見つかる訳には行かない事情が垣間見えたりもする。
・・さてそうなった時、ドラマは何を提示できるか。
男は自分の「不幸」を語るが、なぜその連中が彼の手を奪ったのかについての彼の考えは明らかにしない。左手を取り戻すという決意は、あまりに不条理な扱いを受けた事実に対する、きわめて正当な態度だ、という事は出来る。もしかしたら・・と、観客はその事への思いを馳せる事もできる。が、彼は何かを伏せているのではないか、という疑念を挟む余地も十分にある。自分の落ち度を棚に上げ、怒りに身を預ける事で己の弱点と向き合う事を拒んでいる・・そういう考えるもこのドラマでは自然だ。男が手にとった「手」をドアに投げつけて言う最後のセリフ「畜生!」に、含まれる意味合いは多義的であり、また、彼の人生という大きな荷物に対して吐かれた台詞でもありそうだ。大きな大きな、大事な大事な、人生が「左手」ごとき(とは語弊もあろうが)に左右されてしまったことへの、嘆きをうっちゃろうとする「畜生」であるならば、これは役者冥利につきる大いに含蓄ある「畜生」を放ってほしかった。(またそこまでの演技であってほしかった)というのが感想だ。
このドラマが人物の「変化」の予兆を書き込んで居ないようには思えないのだ。

青いプロペラ
らまのだ
SPACE EDGE(東京都)
2015/11/20 (金) ~ 2015/11/23 (月)公演終了
満足度★★★★
こまやかに書かれたストレートプレイ
劇作家協会新人戯曲賞最終候補に残った作家・南出謙吾のユニットの第一回公演という事だ。地方都市。大型店舗の進出にあおられる既存スーパーが舞台(本店とその支店だけのようだ)。男女関係の発展・変容も話の展開に噛みながら、状況の変化に人物らがどう行動して行くか、変化を受け入れたり挑んだり自分を見詰める様を、観客はつぶさに見て行く。こまやかな作りと、それに適合した役者たちの魅力のバランスが大変よく、俳優の顔がよく見えるし心情もよく分かる、言葉が立ち、心地よい。ドラマ=時間が全体として不可逆に動いて行く硬質さも、spaceEDGEという小さな空間に組まれたセットの中で、しっかりと感じさせたれた。そんな中、不思議にファンタジーな時間が成立する瞬間もあり、それが全体の中に違和感なく、それらをくるめてとても上質な劇だと感じた。

ブルーシート
フェスティバル/トーキョー実行委員会
豊島区 旧第十中学校 グラウンド(東京都)
2015/11/14 (土) ~ 2015/12/06 (日)公演終了
満足度★★★★
雨の中、豊島区の廃校の校庭で
当日は雨だった。小雨ではあったが降っている。ビニール合羽が100円で売られているのを買い、ポリ袋に荷物を詰め、心して椅子に座って観た。
以前書店で立ち読みしたテキストから感じた「世界」を裏切らないタッチで、一人一人がそれぞれのエピソードにおいてスポットを当てられ、語られる言葉はその時間・空間が3・11後の世界で吐かれ、そこに遡り得る時間を生きている主体であることが、横溢している。
初演が、いわきの学校で生徒と共に作られた事と場所との関係が、今回の再演では異なる。どうしたか。・・冒頭、初演時の校長先生の挨拶が大型テレビから流れ、また終盤には今回参加出来なかったキャスト(他は初演時のオリジナルキャスト)が近況を語る録画映像も流れた。キャストの卒業後の現在の立場を語る場面もあって、オリジナルの「ドキュメント」性がそれらによって一貫していた。作品(テキスト)としては、最後に付け足されたらしいシーン・・延々と続くリフレインが、終りを見ない事が分った時(相当時間は経っている)、飴屋氏が終演を告げに出てくる。「グランギニョル未来」公演のラストで飴屋氏自身が叫んだ叫びを思い起こさせる張りつめた、長いシーンだった。
遊び的な言葉や詩の中にドキッとさせられる鋭利さが時として光る。存在の心許なさの中に、「命」が意識される。

オークルチャボット
劇団黒テント
王子小劇場(東京都)
2015/12/05 (土) ~ 2015/12/13 (日)公演終了
満足度★★★★★
黙っていてもいいのだが・・(私的感想)
もう少し長く拍手して手が腫れても良かった。個人的には十数年前、二番目に知った劇団。懐かしさに震える。劇空間のアトモスフィアを観劇後も噛みしめて帰路についた同劇団「メザスヒカリノ・・」(初演と翌2000年の再演)は、演劇との幸福な出会いであった。この時いらい、先日のこまつ座での「再会」に続き、今回の黒テントでの音楽・荻野清子(終演まで知らなかった)は、黒テントにとっても「メザス・・」いらいでは・・。荻野楽曲はドラマとの絶妙な距離感で人物たちを愛おしみ、人生の時間への思いを切なくかき立てる。ドラマ上の結語の後の唄は、「メザス・・」のラストの唄に似ていた。ドラマを俯瞰し、既に現実に帰って行こうとする、<ぼくら>のことを歌う唄だ。贅沢にも数曲ある生演奏は全て登場する役者が自前でやっている。黒テントは何と言っても音楽である。(アトモスフィアを噛みしめた次点は「上海ブギウギ」。)
ファンと言って憚らない滝本直子、服部吉次、やってくれる片岡氏、内田氏、貫禄の桐谷夏子、特徴ある声の山下順子、堅実な宮崎恵治と、黒テントでしか見られない個性の団員総出に胸が熱くなる。
そして、特筆すべきはテキスト。舞台は日本らしいが、アメフトの応援団(サッカーで言う所のフーリガン)の生き様を、ヤクザ映画よろしく描き出す。山元清多の「海賊」を彷彿とさせる、「男気」の競い合いである所の啖呵の応酬、「如何に美しい喧嘩を戦うか」のモデルと見える。わがチーム・オークルチャボットはニワトリ、対するチームはヒラメを渾名とするが、このレッテルを駆使した罵り語の多彩さ。作家の坂口氏が多産の時期を舞台は見逃しているが二、三見た記憶を手繰っても、今回の練られ具合はどうだ。こんなに書ける作家だったのか・・。元々ノワールな世界を得意とするようだがその面目躍如。言葉に酔った。役者も酔えた事だろう。
このお話が女性の支持を得るのかどうか・・と一抹の懸念もよぎったが、今の所材料がない。
昨年の今は無きタイニィアリス公演での「復帰?」から一年。個人的心情でしかないがよくこれを作ってくれたと感涙。斎藤晴彦氏もきっと笑ってる。

お召し列車
燐光群
座・高円寺1(東京都)
2015/11/27 (金) ~ 2015/12/06 (日)公演終了
満足度★★★★
横長な座高円寺1は鉄道モノが正解?
そう言えば以前この劇場で観たとくお組も駅ホームの芝居だった。燐光群は昨年の「8分間」が駅ホームだったが、今回は列車の中、及び奥側はホームにもなる。
今回の燐光群は、いつもながらの「言い合わず」「補強し合う」群衆セリフで多くを説明する場面の割合も高いが、渡辺美佐子の存在も大きく影響してか、程よく重く深みのある芝居になっていた。お召し列車と揶揄された列車に乗り込んだ、究極の差別対象であった「病」の当事者のグループと、20年東京五輪での「おもてなし」案としての「お召し列車」を吟味し決定するべく集った一般人のグループ。過去に繋がる集合と未来を見据える集合が列車の中で行き交うも、二つの問題が並行して重ならない時間は長い。それが一瞬の内に劇的に交わるのは終盤での事だ。両者が手をとり、「あるべき日本」を眼差す厳粛な時間がよぎる。そしてあっと言う間に幕は下りるが、この含意は後から心の中に浸潤し、焼き付いて離れない。

王国、空を飛ぶ!~アリストパネスの『鳥』~
SPAC・静岡県舞台芸術センター
静岡芸術劇場(静岡県)
2015/10/31 (土) ~ 2015/11/15 (日)公演終了
満足度★★★★
左脳的テキスト、右脳的に飛ぶ(快哉)
なぜかこれは観たかった。静岡くんだりまで足を伸ばしたが、甲斐あった。ギリシャ喜劇作家・アリストパネスの現存するテキストの一つ『鳥』は、奇想天外な話で、天(神の国)と地(人間の国)の間、つまり中空に鳥たちが国を作ってしまう。この話の筋は残しつつ、作・大岡氏は現代の話として構成し直し、現代劇としてSPACの劇場にどっかと現出せしめた。これ即ち現代諷刺劇。日本の現代・現在をちくりとやっている訳だが、時々寒くもなる。だが、寒いと感じるのはそれを寒いと感じさせる「空気」を吸って生きる己の偽らざる感覚に他ならない、という事でもある。言葉にすれば身も蓋もない事実も、それが事実なら言葉にすべきである所、我々は何を口ごもり、口にしない洗練さなどと澄ま しているのか・・と。この劇は『鳥』の翻案であると共に、アリストパネス自身が作品を通じて当時の世相や事物を刺しまくったように、日本においてそれをやる、という試みでもあった。この試みに拍手を送らずして何に拍手するものか?などと興奮を噛みしめつつ帰路についたものである。

水仙の花 narcissus
城山羊の会
三鷹市芸術文化センター 星のホール(東京都)
2015/12/04 (金) ~ 2015/12/13 (日)公演終了
満足度★★★★
城山羊3作目、斜に見た感想
岸田戯曲賞を取った前後の舞台を観ていた。リアリティを平然と無視して「娯楽」(即ち意表を突く殺害・濡れ場・裏切りなど)を優先し、観客はそれを良しとして喜んでいる、何と低レベルで下品な空間だろうと、唾を吐きたくなる初回であった。下品さをカバーする「何か」もない(何やら有りそうな雰囲気を醸してるが・・)。ただ、二度目、相変わらずリアリティ無視のテキトーさに再度唾棄したのだったが、「真面目に作ってる」様子がどことなく伺えた。もう一度だけ見てみるかと、今回三鷹くんだりまで足を運んだが、芝居が成立しており、最後まで面白く観た。
終盤で時間経過がおかしい部分があったものの、そこで城山羊の会の特色をいま一度思い出したという事で、そこまでは破たんなく見れた。ただし、ぶっ飛んだ話である事は同様で、これを成立させていたのはひとえに役者の力、とりわけ吹越満の演じる中産階級の狂気と良識の両極に振れるキャラクター、また周囲の者を常軌を逸した行動へ突き動かす謎の女性の美形、肉親でありながら別人である事を否定し受けいれてしまう妹、その夫、謎の女性の夫、男の娘のサディストぶり、彼女と不思議なバランスで関係している彼氏、胡散臭いコンサルタントなど、いずれも常軌を逸した事態を成立させるべくそこに立っている。
城山羊の特色は、あり得ない場所やタイミングで「発情」し行為に及ぶ場面が必ずある、という事らしい(三作とも共通していたので恐らくそうだろう)。
必然性があれば文句は無いがお家芸のようにその場面を仕込む必要はないのではないかと素朴に思う。しかしそれが集客や人気に繋がっているなら、時代のほうがエログロを擁する土壌と化しているのかも。文明の爛熟の中、抑圧状況を身体が感知している・・
お話については特段何か言い添える事はなく、深読みできる余地もないが、ただある場所で、奇妙な出来事が起こり、その事態にあって初めて人間が見せる興味深い反応を、舞台上で描いて見せたものだ、と言える。で、毎度の事、その感情は人間が「追い込まれた」時のそれであり、作者の狙いもそういった修羅場での人間のありようを如何に醜悪に描き出すか、という所にありそうだ。
今回は優れた俳優(チョイス)と戯曲とのマッチングにより、他では目にできない舞台を味わえた、と思う。

ラバウル食堂
劇団芝居屋
ザ・ポケット(東京都)
2015/11/11 (水) ~ 2015/11/15 (日)公演終了
満足度★★★
ディテイルの面白さ
初観劇の劇団。ラバウル食堂、というタイトルが気になり観劇させて頂いた。タイトルはとある商店街の一角にある古い食堂の名前だ。芝居が進むとこれが至極納得なタイトルである。元店主がラバウル戦線からの帰還兵(病気のため玉砕の前に帰国した)、戦友たちから預かった手紙を遺族に渡すために戦後「ラバウル」と名を冠した食堂を出したという。古くなった食堂を改装した娘、その婿や町の人達が結果的にはその遺志を継ぐ事になるお話、と諸々捨象すれば、そういう話である。
面白いのは町の信金の営業青年やブティックの店長、その踊りの師匠雑貨屋、ラーメン屋、肉屋といった面子が「町おこし」が恒常的なテーマとなった町の日常の、なかなかリアルに切り取られた光景を再現しているところだ。
じりじりと逼迫させられている「地方」「地域」の例に漏れないこの町で今イベントが計画されているらしい。そこへ、「ラバウル食堂」とのこの町を探る地域のケーブルテレビの取材が入り、カメラを回す所での、まるでお約束のようなコミカルな場面もある。番組が放映されると皆それぞれの携帯の着信が鳴り、反響に喜び、泣くシーンも用意されている。
最後には、地域を盛り立てようと奔走していた信金のお兄さんの願いも叶わず支店が撤退となり、また日々味と格闘するラーメン屋の倅がついに独立の意志を親父に打ち明け、すんなり認められるといった、そんなエンディング近くのエピソード紹介。
地元を愛し地元で頑張ろうとする人々と、「外」へ出て自分を試したい野心を持つ人との、潜在的な対立構図がこのラーメン屋の息子を通して浮かび上がるが、何故か男は父の承諾を得た途端、東京へ行く気を無くす。「憑きものが取れる」と言うが、「東京」「都会」、ある種パターン化した「成功」の図への囚われは、様々な問題を難題と意識させる大元ではある。
地域の疲弊の問題と、風化して行く戦争という問題が主に盛り込まれた芝居だが、私の常々のこだわり=戦争をドラマの手段として用いる事の倫理的懸念=には抵触せず、人と社会に歴史有り、という単純な事実に気づかせる芝居である。
もちろんこの社会の「日常」がどうなっているのか、という視点が大事なわけで、「のぞき見る」日常は様々に解釈し得るし、切り取り得る。
いずれにしても、この芝居のような平和が続くことが願わしいと思える芝居であった。
