 公演情報
「狂人よ、何処へ ~俳諧亭句楽ノ生ト死~」の観てきた!クチコミ一覧
公演情報
「狂人よ、何処へ ~俳諧亭句楽ノ生ト死~」の観てきた!クチコミ一覧
-
実演鑑賞
満足度★★★★★
鑑賞日2025/03/21 (金) 19:00
大正・昭和の歌人であり劇作家であり小説家だった吉井勇(1886-1960 )は、大女優・松井須磨子が唄い大流行させた「ゴンドラの歌」の作詞家としても知られている。「いのち短し恋せよ乙女~」という歌詞で有名なのは知っていた。
しかし吉井勇が「句楽もの」と呼ばれる作品群があり、「俳諧亭句楽」という落語家と、その仲間たちの騒動を描いたもので、九本の戯曲のほかに「句楽の日記」「句楽の手紙」などの日記体小説もある。それらを通じて描かれているのは芸人たちのもの悲しく、そして微笑ましい生きざまが描かれた句楽ものを連作していた事は知らず、吉井勇の新たな、良い意味で意外な一面を覗けた気がして良かった。
吉井勇作の俳諧亭句楽を主人公にした群像劇の句楽シリーズから九本の戯曲と複数の小説から面白い、不思議な、下らない、物悲しくも笑える話を選んでバランスよく組み合わせて一本の話にまとめられていて、時に笑えて、時に悲哀に満ちながらも、全体としてはあまりに馬鹿馬鹿しいが、それをあまりに真剣になり、何やら魂を作る機会だの、魂の病院だのと句楽は最終的に狂ったかに見えるが、意外と、もしかしたら実現不可能では無いんじゃないかと思わせてくる、妙な説得力があり、圧倒されているうちに終わっていた。
もはや、今の時代、不穏で先行きが見えない社会の中で、魂の病院だの、魂を作る機会だの魂の墓場だのといった一見馬鹿馬鹿しいまでの話であっても、その話にほっこりさせられ、気持ちも晴れ晴れとするんだったら、それが本当に実現可能かどうかはおいといて、その発想は良いことだと感じた。
句楽と仲間たちの基本取り留めもなく、しょうもない話が浅草喜劇のドタバタで話の筋があってないようなハチャメチャ喜劇や、エノケン映画の笑い、落語に出てくる人情的だが、涙に訴え過ぎない長屋連中の笑いといったような笑いが組み合わさったような感じで、登場人物たちもとても個性的で、癖が強くて、日々の嫌なことや、ストレスがたちどころに消えて大いに笑えて、解消できて良かった。 -
実演鑑賞
劇中でソプラノ・サックスを吹いていた徳田さんはバークリーに留学もしていたとか。
他の俳優たちに全然ひけをとってなかったけど、演技とか学んだのかな?
演奏家とかダンサーなんかが演技のレッスンとか受けていなくても、見事な演技してしまうことが、ままあります。
どうなんでしょう?
機会があれば、ぜひともうかがいたいなあ。 -
実演鑑賞
満足度★★★★
大正から昭和にかけての時代設定なのでしょうか。芸人たちの群像劇、とても丁寧な作品作りで、分かりやすく、実に見事でした。ただ個人的には説明的で繰り返されるセリフ(だからこそ分かりやすいのですが)が少し冗長に感じましたが。
-
実演鑑賞
満足度★★★★
吉井勇の歌碑を、何度も目にしたことがあるので、歌人という認識しかありませんでしたが、今回、このような再構築された芸人のお話を観劇し、今まで知らなかった、新たな吉井勇を発見できました。
-
実演鑑賞
満足度★★★★
大正・昭和の歌人、劇作家、小説家である吉井勇の知られざる作品群「句楽もの」は俳諧亭句楽という落語家とその仲間たちの騒動を描いた九本の戯曲と日記体小説。これらの作品は、裕福な境遇にあった吉井勇が社会の底辺で生きる芸人たちに向けたあこがれの眼差しによって描かれている。公演は、吉井勇の心を捉えた芸人たちの姿に想いを馳せながらエピソードを再構築し、失われた下町情緒、生活風景を生き生きと描き出していました。自分はその時代の情緒を知らない年代なので、下町文化が新鮮に感じました。同時に今の時代の人との接し方が、希薄な感じがしてなりませんでした。コミュニケーションについて、どうあるべきか考えさせられる作品でした。良い舞台を鑑賞させていただき、ありがとうございました。
-
実演鑑賞
満足度★★★★★
まぁすごい舞台を観た。
前売り4,500円のレベルじゃない。
歌舞伎ばりの早替わり、息をつかせぬ台詞回し。
絶妙な間。
8,000円、12,000円払って観る舞台より遥かにすごい舞台だった。
まさに「芸人」の集団。 -
実演鑑賞
満足度★★★★
当日パンフによれば、吉井勇の原作で 三代目蝶花樓馬樂をモデルにした人物 =俳諧亭句樂を主人公に、その句樂や句樂の周辺を描いた作品群。公演は、その「句樂もの」の幾つかを遊戯空間(構成・演出・美術 篠本賢一 氏)が再構成し、滑稽洒脱な物語として紡ぐ。その粋な芸人の生き様が生き活きと描かれ、実に抒情や憧憬が豊か。この「句楽もの」戯曲の選択と構成が妙。
吉井勇という歌人で劇作家のことは知らなかったが、「ゴンドラの唄」は黒澤映画「生きる」で知っており、その作詞家だという。哀愁に満ちた印象を持っていたが、開場前に流れる同曲はポップ調でなんとも楽し気である。原作の「句楽もの」は読んだことも観たこともないが、この再構成(換骨奪胎か)によってどのような姿に生まれ変わったのだろう。自分は、この滋味溢れる内容と小気味良い展開は好きである。
幾つかの「句楽もの」を繋ぐのが、桂右團治師匠の語り。これによって場面が変わったことが分かり、物語全体が違和感なく構成される。夫々の場面を通して、当時の芸人たちの暮らしや考え方、そして先にも記した生き様が面白可笑しく立ち上がる。同時に 狂人となった主人公が述べる戯言、しかし そこには現代にも当て嵌まる皮肉や批判が込められている。
また場面変化に対応した舞台美術が見事。同時に「句楽もの」の世界観とでも言うのか、その雰囲気も楽しめた。
(上演時間2時間40分 途中休憩10分)3.22追記 -
実演鑑賞
満足度★★★★★
久々に遊戯空間の芝居空間をがっつり食らった。テキストの文体が何とも味わいがあって大変好み。言葉の文体は「芝居の文体」にも正しく変換され、昭和初期だろうか噺家・句楽を取り巻く者たちの会話や、再現される逸話が洒脱で泥臭くて、演者の佇まいも昭和の調度、着物、江戸口調とも相俟って只々小気味良い。
文学としての戯曲の魅力を放つ近代古典に通じるものがある(小山内薫の「息子」とか、真船豊作品、三好十郎の台詞にも)。
パンフによれば原典は吉井勇の<戯曲>との事。件の落語家を主人公とした一連の作品を篠本氏が構成したものらしい。
こんな作品があったとは、少なからず新鮮な風に思わずむせた。 -
実演鑑賞
満足度★★★★★
2時間40分という長尺の舞台でした。途中10分ほど休憩ありましたが。で、正直、見る人を選ぶ舞台かなと… 私はギリギリ選ばれた側かなと。脚本というか話の構成が私好みじゃなかったかな…と。まあ、これはよしあしの問題じゃなく好みの問題ですが。ただ役者の演技はすばらしかったので星5つです。基本わたしはクリエイターさんの苦労など知っているのでデフォルトで星5つですが^^

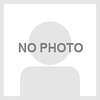 鯉之滝登(168)
鯉之滝登(168)
 ゴージャス(2013)
ゴージャス(2013)
 バート(7524)
バート(7524)
 Shin(399)
Shin(399)
 犬夜叉(8)
犬夜叉(8)
 あかりのこ(1317)
あかりのこ(1317)
 ヨシロウ(1)
ヨシロウ(1)
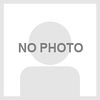 タッキー(4121)
タッキー(4121)
 tottory(2621)
tottory(2621)
 hatayu(631)
hatayu(631)
 ハンダラ(10614)
ハンダラ(10614)