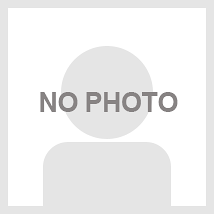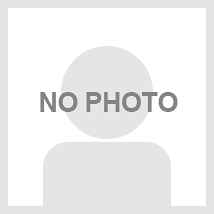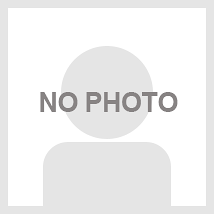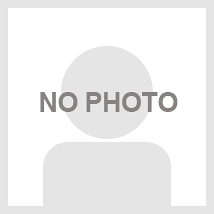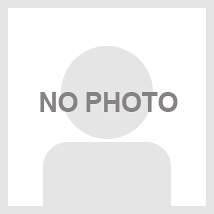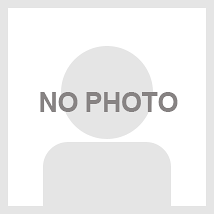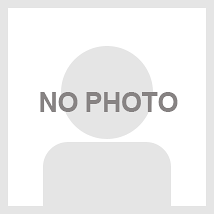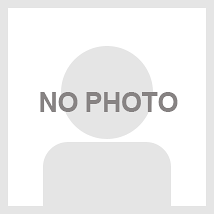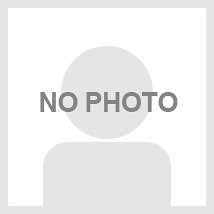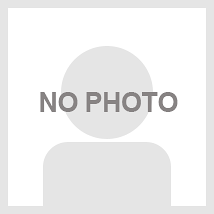※CoRich運営事務局はテーマの真偽について調査を行っておりません。募集情報に応募する前に、投稿者のプロフィールや公式ウェブサイト等をよくご確認ください。
【ご参考】残念な公演の共通点について
-
カテゴリ:フリートーク 返信(142) 閲覧(58656) 2011/09/03 00:46
いつも楽しく観劇させて頂いており、感謝しています。
さて、繰り返しユーザーのレビューで挙げられる不満点(主にスタッフ対応や環境面等)について、整理しました。
芝居の本質ではないところで満足度が下がってしまっては、
劇団・観劇者双方とも不幸だと思います。
ちょっと配慮すれば、改善可能なものがほとんどだと思います。
少しでも参考になれば、幸いです。
【残念なケース】
1.受付の対応が遅い。
これは心証が悪くなる人が多いようです。
できる劇団は受付人数が複数であったり、予約名簿を観客
日ごとに、あいうえお順に作成しており対応が早いですから。
2.開場時間に開場できない。
これも心証が悪くなるようです。
営業時間を遵守できないわけですから。
3.開演時間がアナウンスなく、遅れる。
事情説明がないとイライラする人が多いようです。
個人的には、電車が遅れた時に、車両に閉じ込められている
ような心境になります(笑)。
4.席を詰め込み過ぎる
満員御礼は良いことだと思います。
が、通路も全部ふさいでしまうのは、どうでしょうか。
今のご時世、安全面は大丈夫か心配になることがあります。
また、後方の席からは物凄く観劇しづらくなるという意見も
レビューで見受けます。
5.座席により、観え方が違いすぎる。
小劇場では、前方の座り芝居が多いですが、
後方からは全くみえなかったというレビューをよく見ます。
もし、座り芝居をするなら、舞台のやや中央寄りでの方が
良いのかも。
6.音響が大きすぎて、役者のセリフが聞こえない。
これほど残念なことは無いです。。
事前にチェックした方が良いと思います。
7.出演者の親族が劇中会話してうるさい。
これは結構多いのです。
役者が出てくると、「うちの子なの」的な・・・。
私の体験でもそうですし、レビューでも見かけます。
事前に親族の方には一言お願いできれば幸いです。
8.空調が悪すぎる。
暑すぎたり、寒すぎたりすると芝居に集中できなくなります。
どこの劇団も気にはしていると思いますが、注意しておいた方
が良いかと思います。
芝居が終わった後、客席で仲間同士で文句言っているのを
結構聞くので。
9.誰のための公演か分からない。
「難しすぎて分からない」、「上演時間が長すぎる」、
「不要な役やセリフが多すぎる」と感じるときに辛口レビューが
多いです。
こうなると、公演というより学芸会・発表会に感じてしまう模様。
以上です。
-
>miss youさん
いつもコメントありがとうございます!
私も以前、劇団宛に予約メールした際、返信がなかったことが
ありました。
その時は、やはり電話連絡し予約しました。
(結果的に2週間返信メールを待ちました。)
劇団が予約先、問い合わせ先としてメールアドレスを明記している場合は、確かに早めに返信して欲しいですね。
2013/03/13 00:51 -
>春風さん
いつもコメントありがとうございます!
お察しいたします。。
予約漏れは自分で体験したことはありませんが、
公開処刑?されている人はたまに見かけます(笑)
「早くしてくれ~」と確かに思ってしまいますね(笑)
2013/03/15 00:36 -
<受付について(後編)>
私自身は体験したことがないですが、
レビューでみかけるのが多いのは、
「予約したのに名前がない」というもの。
お客さんに対して失礼だし、信用問題とも思えるので、
事前の準備段階で注意しないといけないと思います。
発生してしまったら、受付が悪いのか、
制作が悪いのかはともかく、
受付の方は誠意をもった対応が必要だと思います。
受付で行列ができないよう、受付をサポートする方が
対応にあたるのがベターかと。
お客さんに迷惑をかけているのだから、
お客さんを放置することはNGです。
再発防止のために、予約経路はお客さんに確認しておき、
同様のことが発生しないように努めた方が良いでしょう。
自由席なら対応次第でリカバリー可能ですが、
指定席だとお客さんの心証は悪いでしょうね。
残っている席になってしまい良席は期待できないわけですから。
やはり事前準備が重要となりますね。
ちなみに、私は「自分が非常に良かったと思った公演」は、
周りの人に薦めています。
昨年のことですが、ある公演を友人に薦め、
後日感想を尋ねたところ、
「非常に面白い作品で演出が素晴らしかったけど、
受付の対応が酷くて頭にきた」と言われました。
「受付の対応が悪かったけど面白かった」ではなく、
「面白かったけど、受付の対応が悪かった」です。
友人には「受付の悪い劇団」という印象がついてしまったようです。
普段は温厚な友人なので、余程のことだったのだと思います。
劇団も薦めた私も友人も、3者にとって残念な結果となってしまいました。。。
やっぱり受付って、とてもとても大事な仕事なんですよね。
2013/03/17 22:18 -
<開演/終演時の挨拶について>
個人的な意見で恐縮です。
挨拶では、主宰の方、脚本・演出家の方にして頂けると
嬉しいです。
どんな方が創り上げた世界観かなのか知りたいからです。
実際には多くの劇団でそうしているのかもしれないですが、
名乗って頂けないことも多く、写真入りパンフレットが
配布されていないと分かりません。
(挨拶前にぜひ名乗って頂きたいです。劇団主宰の○○です。
脚本・演出の△△です。等
開演時はスタッフの方が挨拶することもあるので名乗らない
ことがあるのは分かるのですが、終演時は名乗って頂いた方が
有難いです。
劇団に馴染みのある人には分かるのかもしれないですが。。。)
多分、私と同意見はあると思います。客席で脚本家はどの人
だったのだろうと話しているのを聞いたことがあります。
あと開演が遅延する場合は、スタッフの方ではなく、主宰の方が 予定開演時点で案内した方が良いように思えます。
遅れることはマイナスですが、主宰の方が挨拶することにより、
マイナスイメージは多少和らぐと思えます(ユーザーレビューでも同様の意見を見かけたことがあります)。
2013/03/20 20:19 -
<アンケートについて(前編)>
一般の社会人にとって、自分の仕事を大多数の人にアンケートで
評価してもらう機会はないため、非常に羨ましく思います。
またアンケートをみると、ある程度劇団の姿勢が分かるので、
読むのが楽しみです。
【アンケートによくある質問】
・公演を知ったきっかけは何ですか?
・劇団の公演は何回目ですか?
・感想
鉄板の質問はこのあたりでしょうか。
ところで、公演は誰のためのものなのでしょうか?
この問いに「お客さんのため」と答える劇団はきっと多いと
思います。
ならば、まず一番初めに「本日の公演はいかがでしたか?」と
お客さんの満足度を尋ねるのが筋のように思えます。
また、劇団が知りたいのはこれが一番のはずではないでしょうか。
(実際にはこの質問をしているアンケートは少ないですが)
飲食店に例えると、食事後に「本日の料理はいかがでしたか?」と尋ねられる前に、「当店はネットで知ったのですか?何回目の来店ですか?」と尋ねられている感じです。
思わず苦笑いしてしまいます。。
(ちなみに大劇場公演も同じようなアンケート形式ですが。。。)
ある劇団の主宰が公演後の舞台挨拶で以下のように話されてました。
「アンケートのご協力をお願いいたします。いつも皆さまからお褒めの言葉を頂き恐縮しています。
ただ今後の公演の改善を目的としていますので、お褒めの言葉ではなく、1つで結構です、何かダメだった点を記載して下さい。」
この挨拶を聞いて、アンケートの目的が分かっている、良い劇団だと思いました。
(次回に続きます)
2013/03/23 08:52 -
<アンケートについて(中編①)>
ところで、アンケートの目的って何なんでしょう?
個人的には、公演の問題点の改善・弱点補強、顧客へのサービス向上だと思っているのですが。
もし仮に私がアンケートを作成するなら、構成を以下のとおりにします。私が考えることではないでしょうが、ご愛嬌と思って、広い心で読んで頂けると幸いです(笑)。
1.公演に対する観客の満足度の確認
2.公演に関する各内容の確認
3.劇団の知りたいことの確認
4.感想等の自由欄
「1.公演に対する観客の満足度の確認」については前編で記載したとおりです。
「2.公演に関する各内容の確認」について
公演の問題点の改善・弱点補強のためでもありますし、また個々の仕事の評価があった方が、スタッフの方たちのモチベーションは上がるのでは?と思います。
①脚本②演出③役者④照明⑤音響⑥舞台美術⑦受付⑧誘導係
この位の切り口は必要ではないかと思います。
そして5段階評価にします。
・オーソドックスなら
(非常に良い・良い・普通・悪い・非常に悪い)
・具体的にするなら
例.受付(もっと迅速な対応を・もっと笑顔の対応を・もっと正確な対応を・もっと親切な対応を・文句なし)
等。
目的は統計化することです。公演を重ねるごとに劇団の長所と短所が分かってくると思います。
グラフ化する等すれば、傾向がみえてくるでしょう。
そうそう、アンケートは無記名の方が良いと思います。
観客が知り合いが多い公演だと、全て良い評価でつけてしまいがちだからです。
アンケート無記名だと、公演案内の郵送先(氏名・住所の記載)は、どうするのか?
これは後述いたします。
(次回に続きます)
2013/03/25 00:29 -
<アンケートについて(中編②)>
公演案内の郵送先(氏名・住所の記載)は、別用紙として配布します。
そもそもアンケート結果は、公演に関わった人全員が見て良い情報ですが、住所等の個人情報は見る必要はありません。
本来、「アンケートに答えること」と「公演案内をもらうために個人情報を記入する」という行為は別のはずです。
ただ、用紙を1枚にした方が無駄がないということでしょう。
初めての劇団に個人情報を委ねるのは、結構勇気がいります。
別用紙で記入するようにし、「個人情報については劇団制作担当のみが取扱い、厳重に管理いたします」と言われた方が一般客の信用度は増すと思えます。
コストとの問題がありますが、今のご時世、それだけ個人情報は大事なものだと思います。
コスト対策として、観客全員に配布せず、郵送案内希望の人にのみ配布でも良いかもしれません。(個人的には郵便でなくメール案内で十分ですが(笑))
なお、無記名アンケートには属性(性別・年齢代)欄は必要だと思います。統計を分析するにあたり、細かい分析が可能となるからです。
(次回に続きます)
2013/03/25 20:33 -
<アンケートについて(中編③)>
「3.劇団の知りたいことの確認」
「公演を知ったきっかけは何ですか?」「劇団の公演は何回目ですか?」 等、劇団のよくある質問は3番手あたりが良いような気がします。。
それなりの規模の劇団であれば、ここで観客満足度アップのために 劇団ができることを選択形式でアンケートしてみるのもいいかもです。
例えば、「飲食可能な場所での公演」とか「公演後の舞台裏案内」とか。 「公演後の舞台での劇団員との写真撮影(例えば過去DVD購入特典)」 なんかしたら、結構ニーズがありそうな気が。
でも、色々あってこういうのはNGなのかな(笑)。
劇団、観客ともWIN-WINになれるようなものが良いのですが。
2013/03/26 16:52 -
<アンケートについて(後編)>
分析データ収集として、アンケートは少しでも多く回収できた方が良いでしょう。
回収率アップのため、工夫が必要だと思います。
①アンケート用紙を板に付ける
これだけでも効果はあると思えます。
これを実践している劇団は少数ですが。
・板無しの場合
アンケートを書くつもりでない限り、一度カバンにしまった
アンケートを取り出すのは面倒だと思えます。
・板有りの場合
アンケートを書かないと決めていない限り、
一言は書く可能性が高くなると思えます。
(少なくとも私は書きます。。)
②アンケートに対して謝礼を提供する
スイマセン、広い心でお読み頂けると幸いです。。。
ここまでするかは、回収後のアンケートを有効活用できるか
だと思います。
もし自分なら、回収数を倍増するため検討すると思います。
(もし既に十分回収できているなら、ここまでしません。
来場者の8割程度が目標かな。
例えば1公演300人来場だとした場合、240人のアンケート
回収が目標。現状が120人のアンケート回収状況なら、
検討するでしょうね。2公演分を1公演で回収できるので
あれば。)
とはいえ、高価なものは無理なため、
謝礼は1枚あたり30~40円程度でしょう。
(例えばペットボトルの小サイズ等を安く仕入れ、
アンケート回収時に交換する)
勿論、コストに見合うアンケートでなければ、
検討結果、やらないかもしれませんが。
2013/03/31 22:20 -
ちょっとブレイクタイムです(笑)。
今回は私が出会った残念な客について、述べます。
(非常に残念な客)
飲食禁止・撮影禁止の中で以下の行為を行っていた。
・おにぎりを食べていた。
・携帯カメラで舞台を撮影していた。
どちらも公演後、他の客からスタッフが苦情を受けていました。
しょうがないとはいえ、気の毒になってしまいました。。
(残念な客)
・体臭が非常に臭う、香水がきつい
・遅刻してきて、周りへの配慮ができない
・いびきがうるさい
・上演中、独り言が多い
・上演中、パンフレットをやたら見てカサカサうるさい
・出演者が出てくると、隣席の人と話し出す(出演者が身内の場合が多い)
せっかく良い芝居を観劇していても、隣席がこういうときはテンションが下がってしまいますね。。
劇団のせいでは全くないのですが、不運だと思ってしまいます。
ユーザーレビューでも、たまに残念な客のことが記載されていることがあり、思わず共感してしまいます(笑)
そういえば、前席が大男でみえなかったというのもあったなあ(笑)
あと携帯電話関連(マナーモードの振動音、上演中暗い中で見ている)とか。
2013/04/07 13:34 -
<小劇場①>
春風さんが、小劇場で”疎外感”を感じるという指摘(34番目の投稿)をされていました。
このキーワードについては、私も同意見です。
小劇場観劇を始めた頃は、正直疎外感を強く感じました。。
さて、この話を深堀りする前に、まずは私の周りのエンターテイメント好きな友人たちの話をします。
(小劇場もしくは大学内公演等の観劇経験有の人が多数)
まず、友人たちの「エンターテイメント鑑賞(観劇等)の目的」は、デート、友人との遊び、ストレス解消、現実逃避(笑)等。
要は、「気分良くなりたい、元気になりたい」ということですかね。
私もそうですが(笑)。
この目的を達成できれば良いわけで、友人たちには芝居の他にも映画、ライブ、お笑い等、選択肢が多くあります。
同じお金と時間を費やすなら、気分の良い方を選択するのは当然ということになります。
これは別にエンラーテイメントに限らず、例えば飲食店を選択する時でも同じです。
なので、一般客(ここでは小劇場初心者を指す)を対象とした場合、劇団にとってのライバルは、まずは他劇団ではなく、他のエンターテイメントなのかもしれませんね。あくまで仮説ですが。。
ということで、まず一般客(ここでは小劇場初心者を指す)が来ても、他のエンターテイメントに負けない体制(というか姿勢?)を整えた方が良いと思えるのです。
(次回に続きます)
2013/04/14 22:28 -
<小劇場②>
一般客の集客は
①宣伝(チラシ、各劇団WEB等)
②口コミ(口コミサイト、twitter、知り合いへの口コミ等)
③リピート
で成り立っているように思えます。
その内、一番大事なのは、おそらく③リピートだと思います。
自分が小劇場の存在を知らなかったせいもあり、
当初、一般客が小劇場に多くないのは宣伝や口コミが
足りないせいだと考えていました。
が、最近はそうでないのかもと思ってきました。
あくまで私の周りのことですが、一度くらいは小劇場や大学内公演を観劇している人が結構いました。ちょっと驚きました。
そして、観劇経験から判断して、彼ら、彼女らは小劇場に
リピートしていないのです。
(リピートしない理由)
確認したところ、主に4点ありました。
①芝居に興味なし(ただの付き合いで観ただけ)。
②芝居が面白くなかった or 役者が下手で観ていられなかった。
③関係者の身内公演に思え、居心地が良くなかった。
④利用勝手が悪い。
(次回に続きます。)
2013/04/21 15:02 -
①芝居に興味なし(ただの付き合いで観ただけ)。
これは論外ですね。リピートは難しいでしょう。
②芝居が面白くなかった or 役者が下手で観ていられなかった。
劇団に「ガンバレ!」と声援を送ることしかできません。。
③関係者の身内公演に思え、居心地が良くなかった。
次回後述します。
④利用勝手が悪い。
映画等に比べると公演情報が少ないという意見が多かった
です。不満点は皆、大体同じですね。
ほとんど今まで記載してきたことの繰り返しになります。
・上演時間帯が分からない
⇒ これは公演後の予定が立てられないということです。
映画館のように上演時間帯をチラシやHPに記載した方が
良いと思います。
・あらすじが事前に分からない
⇒ 観劇初心者はチラシに全く記載がないと
それだけでNGのようです。
あと、笑える芝居か泣ける芝居か恋愛ものか、
ある程度明確に分かった方が良いようです。
ちなみに、一緒に観劇した友人(観劇初心者)のほとんどが
その場で配布チラシを選別し、興味のないチラシは劇場に置いて帰っています。
上記の記載がないようなチラシは、持ち帰るのに値しないようです。
数あるエンターテイメントの中から選択する側にとっては、
選別はごく当たり前のように行っています。
このレベルの配慮ができないと、情報戦で他のエンターテイメントには勝てないと思えます。
あと、観劇初心者は、 芝居を観ることだけが目的ではないようです。
「今日観た芝居、面白かったね。」と言いながら、友人と食事したりすることの方が比重が大きかったりします。
なので、土日は14時、19時公演が多いですが、13時、18時公演の方が良いと思われます。
2時間公演であれば、公演後にお茶や食事をゆっくりできるからです。
(次回に続きます)
2013/05/04 00:49 -
<小劇場③>
③関係者の身内公演に思え、居心地が良くなかった。
これが小劇場に足が遠のく主原因といって過言でないでしょう。
なぜ関係者の身内公演と感じるのか?
主な理由は「観劇後の役者面会」にあります。
公演後にアンケートを書いていたら、役者さんが客席で知り合い に挨拶を始め、”疎外感”を感じてしまったという意見が大多数。
コリッチでも、役者さんが知り合いとの話に夢中になり、
帰り道を塞がれるというコメントをみかけます。
あと、開演前にあちこちで「久しぶり~、観に来たんだ?」的な、
明らかに身内の挨拶が行われていたという意見も。
一般客増員を図るなら、何も対策を講じないというのは
得策ではないと思えます。
ちょっと強い言い方をすると、一般客のためではなく、
身内のための公演に感じてしまうからです。
新たな一般客を得ようとしても、これではザルで水を掬うような
ものに思えます。
<対策案>
身内客も大切なお客様なのだから、挨拶はきちんとした方が
良いのは確かです。
私が経験した中で、印象の良かった劇団では次のようにして
いました。
①公演後、役者さんが全員勢ぞろいで、劇場出口で観客に
挨拶し見送る。
→ これは小劇場ならではのサービスだと思います。
観に来た客を大切にしている印象がします。
また観劇初心者には新鮮に映ると思います。
②役者面会希望の客はそのまま客席に残ってもらい、
一般客が退場した後、役者陣が客席に行き挨拶する。
→ 忘れ物を取りに劇場に戻ったので、こういう劇団が
あることが分かりました。
ちなみに、アンケートも記載したので、恐らく知り合いは
公演後10分程度待っていたのではないでしょうか。
少なくとも一般客がアンケートを書き終わる位までは、
役者さんは客席には出てこない方が良いと思えます。
ヒーローショーの後、ヒーローがすぐにマスクをとって
現われるようなものですから全てぶち壊しになります。
配慮は必要と思います。。
(次回に続きます)
2013/05/05 23:10 -
<ご提案①>
接客については個々の劇団が頑張っても、
小劇団全体への浸透は難しいかもしれませんね。。
組織的にやらないと、なかなか難しい面もあると思えます。
ただ、今まで記載したようなことをある程度意識的に行わないと、
「小劇場全体に対する一般客のイメージ向上」は難しいかもしれません。現状維持のような気がします。
(実行した劇団については効果はあると思いますが、そもそも
多くの一般客がどの劇団の公演を観劇するか分からないからです。)
そこで「各演劇祭の主催者各位(事務局)」にご提案させて頂きたいと思います。
素人ですが、色々考えてみました。参考にして頂けるだけでも嬉しいです。
(関係者のお知り合いの方は、「こんなこと言ってる人がいるよ」と
当掲示板をみるようご案内頂けると幸いです。)
<各演劇祭の主催者各位(事務局)へのご提案>
接客(制作・受付等)にスポットを当てる企画として、
①演劇祭にて”接客に関するキャンペーン”を
行ったらどうでしょう?
②接客についても評価対象としてはどうでしょう?
(詳細は次回に続きます)
2013/05/12 23:29 -
<ご提案②>
個人的には、劇団にとって「脚本・演出」、「役者」は車の両輪だと思っています。
そして「接客(制作・受付等)」が3輪目であり、これが加わることにより、安定的な走りが実現すると勝手に思っています。
なので、「接客(制作・受付等)」にスポットを当てるのは、
重要なことに思えます。。
①演劇祭の接客キャンペーン
演劇祭参加団体は、「演劇祭の期間は勿論のこと、
今後、例えば”開演時間を遵守する”というようなキャンペーン」を
行います。
こういう意識づけって意外と大事だと思います。
主催者側で5項目位キャンペーン項目を決めて
それを遵守するというのを学生演劇祭等で行うのも
有効に思えます。
最初は学生演劇からスタートしている劇団が多いようなので。
②接客についての評価対象
優秀な脚本家、演出家、役者の方が表彰されるような演劇祭も
あると思いますが、制作者(制作側のスタッフ)が表彰されても
良いと思えます。
接客が良いという評判の劇団(優秀な制作スタッフ)の
運営が標準となっていけば、観客からみて
現状より更に気持ちの良い観劇環境になると思えます。
(評判の良い制作スタッフの仕事受注が増加する等により、
少しずつ広がっていくということを期待)
このようなことが少しずつ浸透することで、
接客に関する常識が改善されるとGoodだと思います。
1年後、3年後、5年後を考えた場合、
小劇場全体が、一般客にとって現状より少しでも
足を運びやすい環境になれば嬉しいですね。
2013/05/19 16:37 -
<口コミについて>
またちょっとブレイクタイムです。
集客するのに口コミは、有効だと思います。
私自身それで多くの公演に足を運びました。
最初のうちは、面白い作品や魅力的な作品に出会え、小劇場公演に嵌まっていました。
しかし、チラシだけを頼りに観劇を続けるうちにハズレが続き、
小劇場観劇を辞めようと考えていたころに、コリッチに出会いました。
しばらくはユーザー登録をせずに、皆さんの投稿を参照するだけ
でした。
常連ユーザーが多くコメントしているもので、4点以上のものを目安に観劇すると満足度が急上昇しました。
ただ、この方式は公演期間が長いものは良かったのですが、
短い場合はなかなか難しかったです。
なので、次に行ったのは、自分と感性の近いユーザーさんを
探すことでした。
同じ公演を観ても、年齢や性別等によっても感想は違うものになります。
観劇本数が多い人が自分の感性に合っているわけではないです。
感性が近いと思うユーザーさん良いと判断した場合、自分も観劇するというスタイルをとりました。
多少好みは違うものもありましたが、これも有効でした。
ちなみに、私は投稿数が極端に少ない(1、2件)ユーザーが☆5つを連発している公演や辛口コメントをして☆1つの場合は、参考外としています。
多分、こういう投稿はコリッチユーザーには、すぐばれるでしょうね(笑)。
属性みれば、すぐに分かるので。
ただ、一般ユーザーには分からないかもしれないので、
食○○グ等のように投稿数やユーザー支持数等で、
特点の重みづけというのも有効かもしれないですね。
2013/05/26 14:41 -
32でご紹介いただいた「fringe」を主宰している荻野と申します。
ラスカルさんや他の方が書かれている「残念な点」の多くはそのとおりで、私が「fringe」で指摘している内容と重なっています。小劇場演劇で「残念な点」が目立つのは、メジャーとインディーズが同じ土俵で扱われているため、接客などのサービスレベルが不揃いなことにあります。
ラスカルさんは「残念な点」を小劇場演劇全体で改善してほしいという思いで書かれているようですが、私は「残念な点」がある上演団体は淘汰されても仕方がないと考えています。例えば飲食店なら、どんなに料理がおいしくても接客がひどい場合は、二度と行きたくないと思うでしょう。同様に「残念な点」がある団体は、観客に見限られても仕方がないと思います。作品が素晴らしい場合はもったいないと思いますが、それはその団体が自覚するしかありません。
ラスカルさんは「残念な点」があると、初めて観劇した人にとって小劇場演劇全体の印象になってしまい、リピーターを失う結果になると指摘されていますが、そうした団体は、本来なら初心者が足を運ぶべき対象になってはいけないと思います。観劇の幅が広がり、観客自身がクオリティとサービスの折り合いをつけられるようになってから足を運ぶべきで、初心者に紹介すべきではないでしょう。逆に、そうした玉石混合の状態で、初心者に安心して薦められる上演団体がわからないというのが、いまの小劇場演劇の構造上の課題だと思います。
誰でも公演が出来るというのは演劇という表現の可能性でもあり、裾野が広いのはよいことですが、小劇場演劇の場合は裾野と五合目の区別がつかないのが現実です。これが野球なら、プロと草野球の区別は誰にでもわかりますが、小劇場演劇はプロかと思って足を運んだら、草野球だったということがあり得るわけです。
すべての上演団体を一定のレベルに引き上げるのは不可能で、それが出来ないからこそ発展途上と言えるわけです。ならば、観客の側でそれを判別出来る情報が必要だと思います。「CoRich舞台芸術!」もそうした役割を担ってほしいのですが、現在の機能では初心者向けの上演団体を容易に探し出すのは難しいのではないかと思います。
私自身は判別する手段として、公演日数しかないと思っています。下記が「fringe」で具体的に提言した内容となります。2006年に書いたものですが、言いたいことは現在も変わっていません。
ロングラン定着で小劇場演劇から〈負の連鎖〉を断ち切れ!
http://fringe.jp/topics/casestudies/20060720.html
表現者の数が多いのは悪いことではありませんが、芸術ですから誰もが成功するわけではありません。同様に接客も才能であり、すべての上演団体の接客がよくなるとは思えません。現状では、その前提で初心者に薦められる上演団体を選ぶことが重要ではないでしょうか。
「CoRich舞台芸術!」に対しては、芸術面と制作面を別々に評価・採点出来るシステムを提言したこともあります。それを基に書いたのが下記ブログです。この機能はいまからでも採用してほしいと思います。
私ならレビューサイトをこうする(2)「芸術面と制作面を別々に評価・採点出来るシステムにする」
http://fringe.jp/blog/archives/2006/07/06180241.html
2013/06/05 20:45 -
荻野様
はじめまして!
コメントありがとうございます!
荻野さんの書かれているブログを興味深く拝見しました。
様々な考察を行っていらっしゃって、同意できるところが
多いです!!
確かに重なっている内容も多いですね(笑)。
私は以下のとおりに考えています。
①接客について、「指摘されないと気づきにくい点」、「知ってさえいれば 対応しやすい点」について、記載するようしています。
(心がけているつもりです(汗)。)
私の記載した内容を全面的に信用して欲しいわけではなく、
読んだ劇団の方が「なるほど」と納得し、共感できる点について
実行して頂ければ嬉しいと思っています。
「知っているのにやらない」のと「気づいていなくて出来ていない」のは、我々にとって残念な結果は同じでも、意味は違うと考えています。
「気づいていなくて出来ていない」という点があれば、
それを減少できれば良いかなと思っています。
それでも、残念な劇団は淘汰されてもしょうがないと思います。
②「初めて観劇した人にとって小劇場演劇全体の印象になってしまい、リピーターを失う結果になる」という点について。
あくまで私の周りに限った話ですが、初めから小劇場公演を自らの意思で観劇している人は残念ながらいませんでした。
ほとんどは劇団関係者(学生劇団含む)に誘われての観劇でした。
小劇場公演をみている友人に誘われ、観劇している人は、ほんの一部でした。
そもそも自分で選択してではなく、最初はこのように小劇場(学内公演)に足を運ぶ人はきっと多いのではないでしょうか。
どの劇団から観劇初心者が誘われるかは分からないので、小劇場(小劇団)全体の接客レベルを上げた方が良いと思えたのです。
荻野さんがご指摘のとおり、「誰でも公演が出来るというのは演劇という表現の可能性でもあり、裾野が広いのはよいこと」だと私も思います。
ただ、その公演数だけ関係者周辺の観劇初心者が誘われていると思えます。
公演内容そのものが残念だった場合(草野球レベル)はしょうがないですが、
接客面はちょっと気遣いができれば解消できることが多いと思えます。(お金ではなく、少しだけ気を遣ったり工夫すれば良いことが多い)
ちなみに、私の周りの人たちは小劇場公演に対して、「時間がルーズ」という印象を共通して持っていました。
このような「風評?事実?」を解消し、イメージアップが図れたらよいのかなと思います。
「飲食店」と違い、普通の一般人にとって舞台は生活の必需品ではありません。なので一度悪印象がつくと再訪がなくなる可能性があると思えます。
飲食店で言えば、小劇場自体が料理のジャンルだと思います。
「小劇場って言えば、美味しいのは××店だよね」というところまでは、現在、普通の一般人には残念ながら浸透していないような気がします。
個人的には、「小劇場は接客・(内容)がイマイチだから、他の料理にしよう」となっているような気がしています。。
(ゴメンナサイ、私の周りにこういう人がいます。)
一方で評判さえ良くなれば、一般人は現金なもので、足しげく通うようになるということだってありえます。
飲食店だって、高級店ではなく、安くてボリュームがあって楽しめる店が流行っていたりします。
小劇場も「小劇場でしか味わえない工夫」や「気持ちの良い接客」があれば、良い印象が高まると思えます。
(今の時代、マスコミを利用しなくてもtwitter等で一気に高まることだってありえると思います)
なので、できるだけ多くの方に読んで頂き、願わくば共感して頂けると幸いに思っております。
全ての劇団が成功することは難しくても、多くの一般人が観劇することになれば、チャンスは広がると思えます。
以上です。
2013/06/09 21:25 -
効果的な口コミについて
集客には、口コミは有効だと思います。
大きく分けて、口コミには2つあると思います。
・ネット媒体(口コミサイトや個人ブログやtwitter等)を通じた口コミ
・家族・友人・知人への会話による口コミ
結論として、公演について写真撮影可とした方が、
口コミの可能性は高まると思えます。
口クミする側もされる側も写真があった方が話として
伝わり易くなります。
単に文章や口頭で言われるより、興味を惹きやすくなります。
特に学生や若い女性は、一般的には思い出に写真を撮るのが好きな人が多いし、撮った写真を人に見せたがったりします。
個人ブログにもUPするかもしれません。
口コミ効果を期待する劇団は検討してみてはどうでしょうか。
ある程度の人気劇団であれば、下記の例④が効果的と思えます。
(例④については、48番でも記載した通り、DVD購入特典やリピーター特典としても良いかも)
<例>
①公演時間帯の撮影可
②公演前後の舞台セットのみ撮影可
③公演後の役者・舞台セットの撮影可
④公演後の舞台上での客・役者の一緒の撮影可
他のエンターテイメントや大劇場公演、他劇団との差別化を考えた場合、もし可能であるならば、例①~④のどれかを実行した方が得策のように思えます。
(個人的には、①は公演に集中できないのでやめた方が良いと思えます)
以上です。
2013/06/23 21:53
人気テーマ
新着テーマ