Takashi Kitamuraの観てきた!クチコミ一覧

天保十二年のシェイクスピア【東京公演中止2月28日(金)~29日(土)/大阪公演中止3/5(木)~3/10(火)】
東宝
日生劇場(東京都)
2020/02/08 (土) ~ 2020/02/29 (土)公演終了
満足度★★★★★
いやあ面白かった。いわばシェイクスピア劇の名場面集なのだが、個々バラバラでなく、全体が一つのストーリーになっている。浮かび上がるのは、欲望のままに権謀術数の限りを尽くした男の、成り上がりと転落の悲劇。次々人が死んでいく世の非情と無常。そして最後は悪王を倒す民衆の力である。3時間半と長いのに、全く飽きるところがなく、時間が短く感じた。
〇五年の蜷川幸雄演出はDVDで見た。もとの4時間を超える戯曲をカットしたそうだが、まだ4時間あり、これでも長くてごちゃごちゃした印象だった。今回はさらに30分短縮。その結果非常にテンポがよくなった。素晴らしい。
キ印の王次(ハムレット)の浦井健治は新国立でシェイクスピアの歴史劇を続けてきた経験が生きている。緩急つけて客席を沸かせる見せ場はさすが。シェイクスピアの悪役(リチャード三世、イヤゴーなど)を一人にまとめたような高橋一生も後半、凄みを増した。任侠者とお嬢様の双子を演じる唯月ふうかも可愛いうえに芸達者で、貫禄があった。蜷川版では篠原涼子がやっていた役。メイクのせいか今回も篠原涼子に似て見えて、それもまたよかった。
旅籠屋や、二階のある日本家屋を左右二つのセットを組み合わせて作った。美術もシンプルなのに、リアルだったし、転セットをぐるぐる回しての場面転換もスピーディーでよかった。

ねじまき鳥クロニクル【公演中止(2/28 (金) ~3/15(日))】
ホリプロ
東京芸術劇場 プレイハウス(東京都)
2020/02/11 (火) ~ 2020/03/01 (日)公演終了
満足度★★★★★
村上春樹の舞台化を見るのは3作目。一言で言えば言葉は抑えて、身体表現と生演奏の音楽で「ねじまき鳥クロニクル」の世界観を現出させようという舞台。私にとっては未知の、イスラエルの演出家コンビによるものだが、素晴らしかった。物語をなぞることはきっぱり断念しているのがいい。そのくせ原作の筋はきちんとおさえている。「ねじまき鳥」は長いけれども単線なので意外とシンプル。二つの筋が並行するうえに飛躍の多い「海辺のカフカ」より脚色しやすかったとも言える。
蜷川幸雄演出「海辺のカフカ」は長い話をなぞるのがやっとで期待はずれだった。「神の子どもたちはみな踊る」は、短編二つにしぼって災いから世界を守るイメージをくっきり描いていたが、小粒で春樹ワールドとしては食い足りない。今回はそのいずれとも違って見事な成功を収めた。
俳優、ダンサーがコンテンポラリーダンスのように、フィジカルにスタイリッシュに魅せていた。それがダンスのためのダンスでなく、きちんと物語に奉仕しているから、言葉の示す意味と身体表現が結びついていて見ていて飽きない。
特に暴力表現をシンボリックな舞踏的動きで見せ、音楽とも相乗効果を発揮して、陰惨にならずに禍々しさをよく表した。綿矢ノボル(大貫勇輔)がクレタ(徳永えり=姉のマルタと一人二役)を陵辱するシーンは、鳥肌ものだった。
ひとつの人物を複数で演じるシーンが多い。ノボルと夢の中で交わるクレタ、戦争中の蒙古での敵軍将校、井戸へ降りていくシーン等々。これが世界を重層化し、拡大し、見た目も面白かった。
それにしても主役のトオルを成河と渡辺大知と二人で演じるのはどういう意味だろうか? 最初は大劇場の広い空間を埋めるためという発想で始まったと思う。結果として現代人の多義的な人格をしめし、村上春樹の非リアリズムの世界観によくマッチしたと思う。この非リアリズムの物語のビジュアル化は、この舞台の核心で、前記したような人物の多重化や、言葉でなく身体による象徴表現を多用したことによって成功した。村上春樹の長編の舞台がこんなにうまくいくとは、予想を大きく超える出色の舞台だった。

野兎たち【英国公演中止】
(公財)可児市文化芸術振興財団
新国立劇場 小劇場 THE PIT(東京都)
2020/02/08 (土) ~ 2020/02/16 (日)公演終了
満足度★★★★
早紀子がイギリス人の婚約者とその母といっしょに、10年ぶり(数日の帰国を含めれば4年ぶり)に可児の実家に帰ってくる。結婚の報告のためである。実は早紀子はイギリスで失業したために、ビザ更新のための結婚という要素が強い。ふたりが愛し合っていることは事実だが、同棲でもなんの問題もなく、わざわざ結婚するのは別、というのが昨今のイギリスのようだ。
早紀子は、出来のいい兄と比べられて、両親に邪魔者にされ、いつも干渉されてきたと思っている。前半は早紀子の、親が今回も結婚に介入し、自分を支配しようとしているという「思い込み」が目立つ。良心の些細な言葉尻を、悪く悪くうけとめて、いら立ちを募らせていくのである。早紀子役のスーザン・もも子・ヒングリーがいい。日英両語を操りながら、女性らしい不器用な苛立ちを好演していた。恋人役のサイモン・ダーウェンの受けの演技も自然でよかった。
母親役の七瀬なつみも、客を迎えて上品にふるまう母親を好演していた。

東京ノート・インターナショナルバージョン
青年団
吉祥寺シアター(東京都)
2020/02/06 (木) ~ 2020/02/16 (日)公演終了
満足度★★★★
近未来2034年の東京。初演1994年の時は2004年の設定だった。でも、作品の内容に、この年号はあまり関係ない。上演時点での風俗が書かれているわけではないから。ヨーロッパでなにかの戦争が続き、美術品が東京に大量に疎開してきている。その美術館のロビーをいきかう、様々な人・グループの会話、という内容である。
日本人同士のたわいのない会話に比べ、フィリピン人、ロシア人(今は日本国籍取得)、アメリカ人たちの会話に、生き方や政治社会観の違いも込められていて、彼我の差が感じられる。当の外国人のセリフにも「日本人はこういう話を嫌うから」とある。またフィリピン人が平和維持軍にはいるというのを小耳にはさんだ、日本人が「戦争はんたーい」と皮肉る。こんなところにも、日本人の平和意識の強さと、軽さが、海外との対比で示されている。
日本人だけのバージョン以上に、それぞれのグループの違いが民族や国の違いと重なって意味を強めている。
このあと、通常バージョンを観る予定だが、この違いは、どう感じられるだろうか。
「セミパブリック」を場面のキーワードにする平田オリザだが、「セミパブリック」の度合いは、作品により大分違う。「東京ノート」の美術館ロビーは、最も公寄りの設定である。互いに全く知らない7組が互いに知らないまますれ違うので、「ソウル市民」や「冒険者たち」以上に、人間関係は薄く、乾いた雰囲気の舞台である。
多国籍のスタッフで作ったという舞台美術が面白い。天井から垂れ下がった、白い長いモビールのような装飾など、美術館の雰囲気をよく出してい

グッドバイ
東宝・キューブ
シアタークリエ(東京都)
2020/02/04 (火) ~ 2020/02/16 (日)公演終了
満足度★★★★★
笑った、笑った。戯曲も拍車も美術も見事にハマった大変な傑作である。太宰治の原作部分はすぐ終わってしまう(30分くらい)。そのあとのケラの展開が、奇想天外。女たちに「グッドバイ」をいうはずが、逆に次々「グッドバイ」を言われる。田島(藤木直人)が落ち込むところを謎の「大体の占い師」に、元身近な「大食漢」の女性こそ本当に幸せな相手、と諭される。その直後、追い剥ぎに襲われ、世間では死んだと思われるが、実は生きていて記憶喪失になった。というところで1幕終わり。この展開は、太宰治は決して考えない代物。潔い飛躍ぶりが小気味よい。
この大食漢、ことソニン演じるキヌ子が、本作のかなめの女性である。そのソニンがうまい。ダミ声で、やさぐれた演技は大女優・大竹しのぶそっくり。ビックリである。
第二幕は田島(藤木直人)の一周忌の日に愛人、元妻が全員揃うところから始まる。女たちの喧嘩がまたおもしろい。いいアンサンブルである。この多人数の喧嘩はやはり舞台ならでは。小説だと、誰が誰だかわからなくなってしまうし、「〇〇が」「××が」と人物を指定しているうちにまだるっこしくなるだろう。
夫が妻に冷たいのは、甘えているから。仕事と愛人に一生懸命で、妻は棚上げ。妻は夫を愛しているのに、耐え切れずに別れる。この夫婦の関係は身につまされる。(評者に愛人がいるわけではない、念のため)。二幕のふたりが語り合う場面など、しみじみさせるものがある。
最近、今ひとつの舞台が多かったが、久々に弾ける舞台を見て、元気が出た。
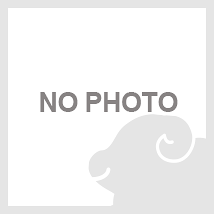
セビリアの理髪師
新国立劇場
新国立劇場 オペラ劇場(東京都)
2020/02/06 (木) ~ 2020/02/16 (日)公演終了
満足度★★★★
楽しくコミカルなオペラであった。技巧的、装飾的というのか、早口言葉のような曲が多い。これはベルディ、プッチーニなどより後の時代の作曲家にはないもの。スタンダールは『ロッシーニ伝』第29章の最後に「声域の〈広さ〉だけでなく、〈装飾音の質の高さと性質〉をも克服しなければならないのだ」と書いて、ロッシーニの歌は難しすぎて、そのうち演奏できなくなると予言した。そのとおり39作のロッシーニの作品で、現在上演されるのは数作しかなくなっている。
「セビリアの理髪師」を見るのは、2016年の新国立劇場公演についで2回目。前回と比べて思ったこといくつか。ヒロインのロジーナは前回の方が可愛かった。後見人バルトロの滑稽さは今回が際立つ。特にロジーナの歌のレッスンの間の黙劇など。アルマヴィーヴァ伯爵は、前回若いハンサムな歌手だったので、ぴったりだったが、今回は太った中年男。流石に若い娘の心を射止める説得力はないかわり、変装などの滑稽味が目立った。フィガロは意外と脇役。それは今回も変わらない。演出は変わらないはずだけれど、前回はヒロインが目立った。今回は男たちのばかし合いが印象に残った。

少女仮面
トライストーン・エンタテイメント
シアタートラム(東京都)
2020/01/24 (金) ~ 2020/02/09 (日)公演終了
満足度★★★★
若村麻由美がとにかくすごかった。真っ白な羽根飾りを背負った宝塚男役スターにして、「嵐が丘」のヒースクリフという愛の亡霊であり、ファンたちの夢にすべてを奪われた肉体の乞食。その上、「男」を装いながら「女」の性に縛られ、満州の満鉄病院で生理の血を流し、怪物・甘粕大尉と出会った歴史的存在。論理を超えた情念と怨念を全身から撒き散らす、鬼気迫る演技だった。
戯曲は有名で読んでいたが、舞台を見たのは初めてだった。なので、ほかの舞台との比較はできないが、70年代の伝説を作った頃と違って、客席の反応がクールなのは仕方がないだろう。前半のタップダンスや歌やギャグで、もっと拍手や歓声で盛り上がってもいいのだけれど。でも、水道男が「(喉がこんなに乾くのは)焼け跡とぎらつく太陽のせい」と言って以降、若村演じる春日野が旧満州へと飛躍するクライマックスは、舞台に釘付けにさせられた。終演後のカーテンコールの拍手は非常に盛大だった。アフタートークがあるので、カテコは二回だったけれど。
若村麻由美の話すセリフがによって、その場にない満州がぱっと立ち上がってくる。唐十郎の言葉の詩的イメージ喚起力をまざまざと感じることができた。

沖縄世 うちなーゆ
トム・プロジェクト
東京芸術劇場 シアターウエスト(東京都)
2020/01/25 (土) ~ 2020/02/02 (日)公演終了
満足度★★★★
沖縄返還直前の1972年、島袋亀太郎(下條アトム)が、引退を口にする。やっと念願かなって祖国復帰で、これから沖縄を良くしようというときになぜ。商売を伸ばしつつカメタロウを支えてきた妻(島田歌穂)と、父とは距離を取ってきた息子(原田祐輔)、「復帰党」の同志ふたりが、米軍占領下での亀太郎のたたかいをふりかえっていく。ほかに妻の友人でやはり商売上手な春子(きゃんひとみ)
現在から、過去をフラッシュバックしていく形式(「生きる」型か)で、亀太郎のたたかいを描く。モデルはご存知、瀬長亀次郎。有名な演説の名文句などもしっかり使っている。沖縄警察で暴動をまとめた場面、さらには那覇市町に当選しながら、アメリカの法律を変えてまでの卑劣な策で追放された場面が一番の盛り上がりだ。「生きる」型にすることで、メリハリのついた評伝劇になったし、父に批判的な息子からの視点で、亀次郎をよく知らない人にも入りやすかったと思う。
「所詮アメリカの前では蟷螂の斧」とか「俺のしてきたことは徒労だったのではないか」という亀太郎の「悩み」(亀次郎の、ではない)を作者は盛り込んでいた。その悩みに対する家族の励ましの言葉は、前半の亀太郎の言葉と重なっている。亀太郎は「勝ち負けなんて関係ない。私たちは戦わなければならないんだ」と言っていたし、「アメリカが一番恐れているのは連帯だ」と人民の力への信頼にゆるぎはなかった。これは亀次郎のものでもある。
「不屈の男」の話を聞いて春子もいつも元気になったと言っていたし、私も亀治郎の言葉に舞台で触れて元気が出た。より良い未来のためにたたかうことの大きな意味をあらためて考えさせられた。
沖縄のたたかいをよく知る人が見ればさらに感動は大きい。終盤では結構、客席で鼻をグズグズさせている人が多かった。

ラ・ボエーム
新国立劇場
新国立劇場 オペラ劇場(東京都)
2020/01/24 (金) ~ 2020/02/02 (日)公演終了
満足度★★★★
ミミのソプラノ(ミーノ・マチャイゼ)といい、テノールのロドルフォ(マッテオ・リッピ)といい、素晴らしかった。2016年にも新国立で同じ演目をみたが、そのときより、はるかによかった。私がオペラに馴染んできたせいもあるだろうが、特にテノールが今回、声に張りと艶があって、高音も見事だった。

からゆきさん
劇団青年座
本多劇場(東京都)
2020/01/16 (木) ~ 2020/01/19 (日)公演終了
満足度★★★★★
明治時代のシンガポールの日本人娼館の物語。女主人のお紋(安藤瞳)がきりっと美しい。女たちの中で稼ぎ頭のミユキ(佐野美幸)は、社会主義者崩れの元学生・七之助(石母田史朗)に思いを寄せる。その恋情が切なく、彼が日露戦争で不具になって帰ってきても支え続ける姿が哀れである。
新劇の代表作らしく、ねりあげられた台詞の美しい芝居である。ミユキと七之助の丘の上の逢瀬の場面など特に美しい。ミユキ「あなたがいて私がいて、日は暖かいのに、あなたは戦争へ行くのね。世間には体は売らないが、心を売っている奴がごまんといる。私たちの仕事はそれより美しか仕事たい」七之助「ロシアは打たなければなりません。理屈です。でも理屈で生きてきましたし、男ですから多少の意地ってものがあります」
女たちが身を売る背景にある農漁村の貧困と、戦争と、彼女たちを最後は安住の地から追い出す国家の横暴。批判するものが明確だった時代はいいとも思った。そういう意味でも戦後新劇の代表作である。
女衒の多賀次郎は意外と影が薄い。様々な過去を持った女たちの群像劇である。その一人ひとりの出自と個性が戯曲でも演技でも、説明的でなくきちっと描き分け、演じ分けられている。お紋、ミユキの出自ははっきりしないなど、無理に埋めない隙間もあって、そこがいい。女たちに最後は捨てられる多賀次郎は無様で滑稽。そこに女たちが「捨てられたふりして、逆に捨ててやった」国家も重ねられている。
切なく美しい群像劇を、常に背景に広がる海が見守っている。冒頭の天草からシンガポールまでつながるその海は、「海、美しいのね」という最初のセリフとは裏腹にどんよりと灰色で、時代の暗い荒波を象徴しているようだ。
2時間20分(休憩15分込み)。私の見たときはアフタートークがあり、演出の伊藤大氏が出て、毎日新聞の濱田元子氏の司会であった。

『どんとゆけ』
渡辺源四郎商店
こまばアゴラ劇場(東京都)
2020/01/25 (土) ~ 2020/01/26 (日)公演終了
満足度★★★★
手錠で腰縄で茶の間に連れてこられた若い死刑囚に、目のギラギラした美人が「似合ってる!」と嬉しそうにいう。そんなブラックユーモアからはじまって、死刑員制度で被害者の老父と若い妻と、見守りの刑務官が死刑執行までの1時間を、一緒に過ごす。かつて死刑を執行していた刑務官の、死刑執行の、踏み板の開いて、落ちる音が耳をついて離れない、のセリフが良かった。
被告と文通し獄中結婚したという女性(最初から出た美人)がいることで、演劇になったと言える。出ないと、死刑囚と被害者家族のぶつかり合いだけになる。刑務官がいるだけでは、この単純な構図は破れないが、この変な女性の存在で、人物たちの関係が複線的立体的になり、バランスも取れる。
俳優はみな好演。死刑囚の嗚咽や、腰の立たないほどの恐怖などなど、言葉にならない感情をみなぎらせて、特に良かった。
80分休憩なし。2008年初演の三演目だという。

悪霊
CEDAR
シアター風姿花伝(東京都)
2020/01/23 (木) ~ 2020/01/29 (水)公演終了
満足度★★★★
「悪霊」は20数年前に読んで、なかなか怖い小説だった。今回、舞台を見て、かなり忘れていたことを思い知らされた。改めて発見することも多かった。冒頭の語り手役が言ったように、西洋の自由主義思想家のステパンという人物がいたこと、その影響下の青年たちの起こした事件だということ、全く忘れていた。それとも、これはカミュの脚色なのか? いずれにしても、ドストエフスキーによる革命思想・社会主義運動の批判である本作の思想的構図が、はっきりする設定である。
休憩10分込みで3時間半の長丁場の劇。マリア兄妹は「カラマーゾフの兄弟」のように、醜い第三の男によって殺されるし、悩めるスタヴローギンは、ラスコーリニコフのように聖女によって信仰を取り戻す(ただ、その結果は真逆)。というように、ドストエフスキー的世界をたっぷり堪能できた。
個々の人物像もわかりやすいし、生き生きしていた。戯曲と演技、演出の総合的な成果であろう。余計者インテリのステパン、内気な聖女・ダーシャ、奔放な女リーザ、陰謀的革命家ピョートルなど。「悪霊」ではスタヴローギンが著名なキャラクターだが、ピョートルのことをすっかり忘れていた。キリーロフを思想的自殺に追い詰めるのもスタヴローギンと思い込んでいたが、実はピョートルだったとは。西欧自由主義思想の実践者をこの二人に、性格を分けたところが、この作品に一層の深みをもたらしたと言える。
殴る蹴る、倒れる、転がる、泣く叫ぶ、嘆く怒鳴る…。登場人物のぶつかり合い、喜怒哀楽の振幅が大きくて、大変な迫力だった。これぞまさにドストエフスキー的。秘密結社の青年たちの「奴隷の平等」思想とリンチ殺人の論理は、スターリン体制から連合赤軍事件・オウム事件までも予見したかのようだった。身につまされる、とは言わないけれど、ドストエフスキー世界の深淵にふれることができる貴重な舞台だった。
先日のシアターコクーンの舞台「罪と罰」より、ずっと登場人物もリアルで、苦悩と葛藤に迫力があったし、重層的なプロットで飽きさせないし、思想的にも突き刺さるものがあった。

FORTUNE(フォーチュン)【北九州公演中止(2月28日~3月1日)】
パルコ・プロデュース
東京芸術劇場 プレイハウス(東京都)
2020/01/13 (月) ~ 2020/02/02 (日)公演終了
満足度★★★
いいところもあるのだけれど、一言で言えば「なんか盛り上がらない」。これは劇作教本的に言うと、起承転結の、「転」における直前と最高点の落差が小さいということになる。一番盛り上がるのが「承」にあたる1幕の終わりの米国西海岸のビーチ場面。悪魔(田畑智子)と契約したフォーチュン監督(森田剛)が、なんでも思いのままにできるからと、嫌味な映画プロデューサーをヤギに変えたりして、相手を震え上がらせるところ。
その後、2幕では、契約してまで手に入れた恋人マギー(吉岡里帆)が去っていく(フォーチュンはなんでもできるのに、あえて止めない)など、あとは破滅へ一歩一歩進むだけで、展開が一本調子。
さらに言えば、動きが小さくて、大劇場の広い舞台を埋められていないのも、印象を弱くする。
田畑智子の悪魔は、蠱惑的で、妙な明るさの裏に荒みがあって、素晴らしかった。

スティングガールズ
首都演劇部
ザムザ阿佐谷(東京都)
2020/01/10 (金) ~ 2020/01/19 (日)公演終了
満足度★★★
基本的には良かった。満開間近のアイドルたちを間近に見られたし、とくに荒井レイラが美しかったし、演技もよかった。工藤美桜はしゃしんでみるのとちがって、スポイルされた性格ワル女のヤサグレ感が出ていた。
結局女性4人が、みんなのアイドルだった野良ミケ猫をひいた犯人を探し出すのだが、そのラストのひねりでが良かった。全体は子供っぽい中、岩谷健司にオトナの存在感があったし、野村啓介のヤクザ青年の演技も、その後の気弱青年との落差で面白かった。見事なヤクザぶりには、女性出演者たちも笑いを抑えるのに大変そうで、こちらも笑えた。

『国府台ダブルス』
filamentz
新宿村LIVE(東京都)
2020/01/22 (水) ~ 2020/01/27 (月)公演終了
満足度★★★★★
笑えた、笑えた。卒業式の「日の丸」「君が代」をめぐるシチュエーション・コメディー。今の日本のどこにでもありそうで、ここまでのしっちゃかめっちゃかはない。最初は「わざとら」や一本調子に思えたが、一癖も二癖もある脇役が次から次へと乱入してきて、笑いが弾けるようになる。
全く初めての集団だったが、この笑いのセンス、タイミングはなかなかのもの。周りみんながジコチューだったりちょっとネジの外れたボケ役の中、一人ツッコミ続ける津和野諒(宣言美術も担当の才人)が笑いをもたらす。なるほど、ツッコミの効果はこういうことか、と改めて発見した。クライマックスの彼の告白も爆笑。
役に立ちそうで全く立たない自己陶酔型美術教師の中田顕史郎、お節介サヨク保護者の前田綾香、前任校の卒業式が気になって本校では全く自己というもののない教師・矢吹ジャンプなど、など。ひとりひとりの登場人物にリアリティーと説得力があった。生徒の役よりオトナの役にそれはいえる。
模造紙に立派な式次第を書くたびに、簡単に破いて捨てるという、潔い演出も、盛り上げに大いに一役買った。情けない美術部員の土橋銘菓、「ミュージシャンですから」が口癖の吹奏楽部長・淺越岳人も笑わせてくれた。
こう書くと、主役が脇役に食われたかのようだが、そんなことない。国旗・国家実施派の校長と女性英語教師、反対派の生徒会長・熊谷有芳(衣装もやっていてびっくり)、そしてなにより、板ばさみになる卒実委員長の榎並夕起が、しっかり舞台の柱になっていた。アイドル役の雛形羽衣もよく目立っていた。
ずっと卒業式のステージ裏だった舞台が、最後の方で、ステージ正面の演壇もバックに現れるという方法もよかった。放送室がすっと現れる装置も、いいアイデアだった。終盤に二転三転するプロットも見事。作・演出の富坂友も抜群のセンスの持ち主である。

阿呆浪士
パルコ・プロデュース
新国立劇場 中劇場(東京都)
2020/01/08 (水) ~ 2020/01/24 (金)公演終了
満足度★★★★
赤穂浪士の「忠臣蔵」を、阿呆浪士の「おまつり蔵」に換骨奪胎する。八(戸塚祥太)が、長町小町のお直(南沢奈央)の樹をひきたいばかりに、「俺は赤穂浪士だ」と名乗るのがきっかけだが、そのまま突っ走るほど科単細胞ではなく、何度も引き返そうとするのに、そのたびに、いろんな見栄や反発からかたき討ちへと突っ走っていく。緩急と名セリフをちりばめた戯曲がよくできている。
演出と役者も笑いのツボをよく抑えていて、楽しめた。
討ち入り場面の立ち回りも見ごたえ=「聞きごたえ」があった。というのは、刀と刀が打ち合う効果音を流すことで、実際には刀がぶつかっていないのに、斬り合っているように見えたから。なかなかの迫力だった。ただ、最後はみんな切腹して死んでしまうので(そこは忠臣蔵ですから)寂しかった。無言劇も切なかった。

アルトゥロ・ウイの興隆
KAAT神奈川芸術劇場
KAAT神奈川芸術劇場・ホール(神奈川県)
2020/01/11 (土) ~ 2020/02/02 (日)公演終了
満足度★★★★
かなりハードルの高い戯曲で、へたをすると歴史の解説やあらすじを追いかけるだけになってもおかしくない。上演時間は今回だって休憩込み3時間5分と長い。そこを、草彅剛というオーラをまとった俳優と、ギンギラの大音量ソウルミュージック(ボーカルは大阪弁)を前面に、コンサートのようなノリで、この歴史アイロニー劇をくるんだところがみそ。薬でトリップさせた替え玉を犯人にさせてしまう放火事件裁判、ローマ(レーム)の粛清、等々、見どころもたっぷりあった。
最初はシカゴのギャングの話(補助金詐欺、商人シートの自殺とか)に、初期のヒットラーのどういう史実が重なるのかわからず、(字幕で理解するものだから)理屈っぽいように、説明っぽいように感じたが、後半は、国会放火事件、オーストリア併合とよく知っている史実を踏まえたものなので、すんなりブレヒトの皮肉や舞台の盛り上がりを楽しむことができた。
こんな怖いウイを支持するか、観客に問いかけ、マシンガンをぶっ放しておどす。最前列の観客は演出の狙い通り、支持の手を挙げていたが、そのより後の反応はちらほらだった。いつものことだが、日本の観客はちょっとおとなしいところが残念。これが本当に観客が熱狂したら、見事なアイロニー劇になるのだけれど。アメリカやドイツではうまくいくのだろうか?

「明日の幸福」「神田祭」
松竹
三越劇場(東京都)
2020/01/02 (木) ~ 2020/01/20 (月)公演終了
満足度★★★★
初めての新派体験。「明日の幸福」、1954年初演の政治家の三代が同居するホームドラマです。意外と(失礼!)今日的な内容で、すっかり見直しました。やはり現代のお客さんを呼ぶ舞台ですから、古臭いものでは通用しません。
騒動のタネとなる家宝の埴輪は、古い家父長制と女を縛る因習の象徴なんです。それに振り回される、女たちのあれやこれやが笑いを誘い、最後には、民主主義の時代の新しい生き方が浮かび上がるみごとなエンディングでした。
波乃さんの時折見せるコミカルさと、水谷八重子のガラガラ声の迫力が印象的でした。
面白くてためになる。いい意味での大衆性と啓発性を兼ね備えた舞台でした。

雉はじめて鳴く
劇団俳優座
俳優座劇場(東京都)
2020/01/10 (金) ~ 2020/01/19 (日)公演終了
満足度★★★★
人間関係の微妙な距離、甘酸っぱい三角関係、愛情一歩手前の親密さを巧みに描く横山拓也らしい舞台。小劇場とは違って、広い舞台を、効果的に使った演出もよかった。
高校の女性教師ウラカワ(若井なおみ)を避難所にする男子生徒ケン(深堀啓太朗)。サッカー部の新キャプテンになった彼の家は、母親(清水直子)が夜勤に疲れ、酒に頼って家事はできず、ケンが主婦代わりである。いわゆるヤングケアラーとして、健気に母を支えているが、もう限界になっている。父親は母親を見捨てて家を出たまま、2年以上帰ってこない。
一方、新しく学校に赴任してきたカウンセラーのトモエ(保亜美)に、ケンに思いを寄せる女子マネージャー(後藤佑里奈)が、ケンとウラカワが抱き合っていたのを見たと相談を持ち込む。はたしてケンとウラカワは教師と生徒の一線を超えてしまったのか。独身のウラカワは、不倫関係にあるトガワ先生(宮川崇)との関係も終わらせたい。シリアスなドラマに、空気の読めないおせっかいな教頭(河内浩)が笑いをおりこみ、スピーディーで緩急のある舞台は、非常に濃密な時間を作り出す。
俳優は母親役の清水直子や教頭役の河内浩の脇役がしっかりと要所を締め、ウラカワの若井なおみとケンの深堀啓太朗の主役は、落ち着いた抑制的な演技でよかった。カウンセラー役の保亜美が教頭に次ぐ、第二のトリックスターで、洒脱な演技で笑いを誘っていた。

『荒れ野』
穂の国とよはし芸術劇場PLAT【指定管理者:(公財)豊橋文化振興財団】
ザ・スズナリ(東京都)
2019/12/18 (水) ~ 2019/12/23 (月)公演終了
満足度★★★★★
中年以降の夫婦で、夫(あるいは妻)と異性の友人との親しい関係が、妻(夫)の苛立ちをよぶという話は、よくあることなのだろう。親しい関係というのは友人としてで、不倫未満のものだ。劇作家にとっても観客にとても切実な問題なのか、昨年から見た新作の中でも、蓬莱竜太「消えていくなら朝」、横山拓也「逢いに行くの、雨だけど」など、秀作ぞろいだ。ちなみに、「男はつらいよ お帰り寅さん」も、吉岡秀隆と後藤久美子のそういうビミョーな関係がメインテーマである。今作「荒れ野」も、素晴らしい傑作。笑いと、切なさに満ち満ちていて、感情を大きく揺すぶられた。本当に夫婦関係は奥が深い。演劇のネタの宝庫だ。
大火にあうショッピングセンターが「ウエストランド」で、のばすと「ウエ―ストランド」=荒れ地になるという、タイトルの解題は面白かった。セリフで堂々と解説してみせるなんて、やられた。「私たちはみんな荒れ地の住民」という小林勝也演じる老人の言葉に、なるほど、とうなずかされた。
