 公演情報
「映像都市」の観てきた!クチコミ一覧
公演情報
「映像都市」の観てきた!クチコミ一覧
-
実演鑑賞
満足度★★★★
もっとシリアスな展開なのかと思って見に行ったので、振れ幅が大きくて腑におちませんでした。斜陽産業となってしまった時期の、映画に対する愛情は感じられました。私が行っていた映画館もいくつか無くなってしまいました。新しい映画館、特にシネコンでは映画館の匂いなんてないのでしょうね。
舞台美術が良かったです。 -
実演鑑賞
満足度★★★★★
面白かったです。
3つの話が交錯した不思議な世界でした。
登場人物達の、辛くても映画を愛しているという気持ちが伝わってきて、切なくなりました。
観客を楽しませる演出も良かったです。
素敵な舞台でした! -
実演鑑賞
満足度★★★★
成程・・・鄭義信の初期作には「千年の孤独」「人魚伝説」「愛しのメディア」と魅惑的タイトルが多かったが本作もその一つ。幕が開くと、、鄭戯曲に欠かせぬアイテムがきっちり揃い踏みである。それらは清新で衒いなく、若き作家の衝動を素直に伝えて来る。自分的には胸キュンである。
鄭氏が新宿梁山泊を離れる最後の作品となった「青き美しきアジア」以前の上記作品は未見であったので念願叶って嬉しい。
StTRAYDOGなる劇団のノリも百聞は一見に如かず、興味深く拝見した。
難点を先に言えば、役者の演技を超えて来る音楽(抒情的な曲のチョイスか音量のせいか)が、「そこは役者の身体を通してドラマを感じたい」という瞬間があった。主だった役には劇団的に中堅と思しい演者を配するも「若い」範疇〔私の目には)で全体的に若く、微かに生硬さを残す。主宰がこの演目を彼らに課する心根が(勝手な想像だが)思われる。
奇しくも同氏による間もなく上演の「キネマの大地」が恐らく映画の撮影所が舞台の芝居だろうので、楽しみ。
本作元々は(チネチッタ)というのがタイトルに付いていて、フェリーニが良く描く撮影現場の狂騒が本作にもあって面白い。そして演劇ならではのドラマ上の仕掛けが映画というテーマと重なる。映画への、人生へのオマージュとなる。 -
実演鑑賞
満足度★★★★
1970年代前半、地方の映画館が次々と閉館して衰退、映画が売れない低迷期が舞台。今の映画しか知らない世代には、映画の転換期の設定に関心を惹かれる。物語は3つの時間・場所も異なるストーリーが並行して進む。映画に夢を抱きながら、アイスクリームを館内販売して斜陽な映画館の経営に苦労する夫婦。撮影現場でわがままで中身のない大監督に無理無体を言われながら苦労する若手脚本家と芋役者ながら親の七光でギャラのことばかり気にする俳優や無尽蔵に消費される資金集めに苦悩しているプロデューサー。足の悪い中年と彼の面倒を見てくれる姉弟。彼らの生活の周囲を現実の世界と映画の中の世界を交差させながら、三つの世界が一つに繋がっていく。個性あふれる役者陣が活き活きとして小気味良い。所々入る踊りや歌も楽しかった。また、劇場を作中の映画館に見立て前振りから芝居に入っていく演出や映画館長がプロマイドやパンフレットをリアルでも売り歩く演出は、臨場感が高まって効果的だった。なお、副題のチネチッタはイタリア・ローマ郊外にある映画撮影所で、 イタリア語で映画を意味する「cinema」と都市を意味する「città」を合わせた造語。
-
実演鑑賞
満足度★★★★★
面白い、お薦め。
1970年代前半、日本映画の低迷期が舞台。映画好きの主人公の過去と現在を行き来し、その哀感と郷愁が相まって叙情豊かな物語を紡ぐ。時代背景には、素朴な日本の原風景と高度成長期へ といった過渡期の世態が垣間見える。脚本(物語)は、斜陽した映画館の中で、若かりし頃の思い出(夢想)に浸っている といった閉塞感を漂わせている。一方、演出は歌や踊りを交えエンターテインメントとして楽しませる。この哀歓するような世界観が好い。
また舞台美術が秀逸で、時代と心情を巧みに表出し 情景も鮮明に映し(描き)出す。その光景は、現在を1970年代前半とすれば、子供の頃は戦後間もない混乱期、青年期は映画全盛期といったことが分かる装置になる。薄昏い中で 手際よく場転換をするが、それによって集中力が途切れることはない。そして この劇場を映画館に見立て、観客を劇中へ誘い込むようなリアリティ。
登場人物は個性豊かな人々で、その化粧や仕草 そして衣裳に至るまで観(魅)せ楽しませる。本筋は、主人公が過去の自分と向き合い、映画こそが生き甲斐だと改めて知る。しかし衰退していく日本映画、それに伴って地方の映画館の行く末も知れてくる。笑い楽しませる中だけに、主人公の悲哀が際立ち印象深くなる。実に巧い。
(上演時間1時間45分 休憩なし)【Aチーム】

 まなぶう(1112)
まなぶう(1112)
 Shin(399)
Shin(399)
 KIKI(9)
KIKI(9)
 みなみ(3316)
みなみ(3316)
 あかりのこ(1319)
あかりのこ(1319)
 こぴ(3891)
こぴ(3891)
 ハンダラ(10620)
ハンダラ(10620)
 ナオ(148)
ナオ(148)
 さらさら(622)
さらさら(622)
 ゴージャス(2030)
ゴージャス(2030)
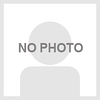 あおぞら(50)
あおぞら(50)
 tottory(2637)
tottory(2637)
 aoaioa(58)
aoaioa(58)
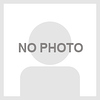 犬夜叉(8)
犬夜叉(8)
 タッキー(4127)
タッキー(4127)