 公演情報
「旅するワーニャおじさん」の観てきた!クチコミ一覧
公演情報
「旅するワーニャおじさん」の観てきた!クチコミ一覧
-
実演鑑賞
満足度★★★★
鑑賞日2025/04/16 (水) 13:00
最後の西村由花さんが演じるチャン セミの感情の爆発、俳優の方の苦労を思う。演技したことがなくて、あの状況を引き出す/導く手立ては想像が及ばないけど、ひたすら恐れ入る。もちろん演技全般がそうなのだと思うが、あの場面がある意味唐突な、あるいはその感情を作る前の場面がなかったと思うので。
平吹敦史さん、佐乃美千子さん、金聖香さん、西村由花さんの演技に魅かれた。
韓国演劇を拝見する機会は多くないが、この作品、韓国の社会/世情/人間関係が投影されていると思うが、人と人と人。それにしても酒を飲むシーンのなんと多いことよ! -
実演鑑賞
満足度★★★
『ワーニャおじさん』
アイルランドのブライアン・フリール翻案による1998年初演作品。
『ワーニャ伯父さん』はつまらないと思っていたがこうして観てみると面白かった。成程、提示され構築された関係性にシェイクスピア的多情多感な情緒、エッセンスを振り掛ける訳か。この関係性のどこに一番思い入れるかのセンス。凄く勉強になった。
二面向かい合わせの客席はガッチリ入っていて『寂しい人、苦しい人、悲しい人』よりも席を詰めている。青年団テイストで客入れから役者がステージに登場、役として日常を過ごし場の空気感を醸し出す。どこからか風が吹いている。窓の外の天候を意識させる演出。
主演ワーニャ役、柳内佑介氏はオリラジ中田っぽい。47歳設定にしては若い印象。敢えてこういうキャスティングにしたのか。
アーストロフ医師役、内田健介氏は巧すぎて鼻についた程。どんどん格好良く見えてきてクライマックスではレット・バトラーのよう。
元教授セレブリャーコフ役、大原研二氏は高須クリニックの高須克弥に見えた。
皆が恋する彼の後妻エレーナ役に佐乃美千子さん、流石。
ワーニャの姪っ子ソーニャ役に渡邊りか子さん。
場面転換として白く長いカーテンを客席前二面に引く。様子がうっすらと透けて見え、舞台装置の移動や立ち位置の指示等普通に聴こえてくる。芝居全体が少しメタ的な方法論の演出で役者が時折観客に台詞を投げ掛けもする。
前半、古典戯曲の取っ付きにくさ、ロシア人名と関係性の判り辛さから客席もぼんやりと思いきや、どっこい後半からかなり盛り上げた。
二作品をセットで観た方が楽しめる。作品の構造についてよく解る。
是非観に行って頂きたい。 -
実演鑑賞
満足度★★★★★
2作品を観劇させていただきました。原作に忠実で非常に見易かったです。チェーホフ好きとしては納得させられました。カーテンの仕切り方が良いと思うし、終わり方も好きです。韓国版の方ですがとても、引き込まれました。終わりも考えさせられた。
-
実演鑑賞
満足度★★★★★
「ワーニャおじさん」、「寂しい人、苦しい人、悲しい人」、両方観させていただきました。2作品を楽しむことができてとても良かったです。
皆さんの熱演、熱量が素晴らしかったです。
そして2作品を同時に演出された伊藤毅さん、大変にお疲れさまでした!!
「パンケーキの会」さん、これからも良い作品を楽しませてください。 -
実演鑑賞
満足度★★★★★
今回の二本立て公演は、是非二本とも観ることをお勧めする。両方観ると全体の趣旨が良く理解できるからである。「ワーニャおじさん」ではチェーホフ原作の翻案と素直に理解できる作りと演出だが、「寂しい人、苦しい人、悲しい人」では作風が全く異なるからだ。この企画自体が抜群であり、演出も各々の作品を深く理解し活かした演出で素晴らしい。追記2025.4.13 14時
-
実演鑑賞
満足度★★★★
韓国のユン・ソンホの“現代韓国版ワーニャ伯父さん”だという『寂しい人・苦しい人・悲しい人』。人物の配置や展開などに「ワーニャ伯父さん」を感じさせるが、何だか90年代半ばの台湾映画を観ているような印象の舞台。約130分。
-
実演鑑賞
満足度★★★
『寂しい人、苦しい人、悲しい人』
凄く脚本は好きなテイスト、作家(ユン・ソンホ氏)は映画として書いたんだろう。やりたいこと、伝えたいことはよく判る。だが演劇となるとまた少し改変が必要。そもそもの媒体の仕組みの違い。テーマは「大人のモラトリアム」。自己決定を遅らせて時間稼ぎをしたところで同じこと。痛みは同じだけついて回る。
天井に吊るされた二本の蛍光灯が意味ありげに点滅を繰り返す演出。やしゃごの『きゃんと、すたんどみー、なう。』でも使っていた手法。基本、酒飲んでグダる描写が続くので真面目に仕事に励む虚しさも欲しい。ソジュ(韓国焼酎)の緑の小瓶で人気のチャミスル、ピーチ味。やたら皆飲む。中身は水だとしてもかなりの量になる。
舞台は現代の韓国、2018年ソウル。硬派な言論が売りの雑誌『時代批評』、売り上げがヤバく梃入れで新編集長(西本泰輔氏)が赴任。この雑誌に人生を捧げているチーム長〈デスク〉(平吹敦史氏)は不満気。編集長はグラフィックデザイナーの美女(金聖香 〈キム・ソンヒャン〉さん)を秘書のように帯同させている。チーム長の古くからの友人、大学院で哲学を学ぶ研究員(荒井志郎氏)がいつものように顔を出す。
自分的には『ワーニャ伯父さん』風味はゼロ。言われなきゃ気付かないだろう。
ワーニャ(捨て鉢の主人公) チーム長(平吹敦史氏)
アーストロフ(医師) 先生(荒井志郎氏)
ソーニャ(医師に恋する) 編集者(西村由花さん)
セレブリャーコフ(大学教授) 編集長(西本泰輔氏)
エレーナ(後妻) デザイナー(金聖香 〈キム・ソンヒャン〉さん)
経理の佐乃美千子さんは髪型を変えただけでガラッと印象が変わる。美人は得だな。舌っ足らずの甘い声は声優向き。
金聖香 (キム・ソンヒャン)さんがえらく美しい。藤村志保の生き写し、目を奪われる。
西村由花さんは初代タイガーマスク(佐山タイガー)のイラスト・トレーナーを愛用。
平吹敦史氏の靴下が破れていたのは狙いか。
西本泰輔氏の吹くシャポン玉。
荒井志郎氏がトニー・レオン顔なので、ウォン・カーウァイの『花様年華』や『2046』の雰囲気。(大好きな映画だったが全くと言っていい程内容は覚えていない)。
荒井志郎氏、平吹敦史氏、佐乃美千子さん、金聖香さん4人でクラブのようなBARのような店で飲む場面、店内に掛かっているフュージョン曲が良かった。
ゆっくりと滅んでいく時代の中で取り残されたような気持ちになる者達。チャールズ・ダーウィンは「最も時代の変化に敏感なものだけが生き残る」と記した。生き残れないと知った連中がふと失くしてしまったもののことを思い返すような日暮れ時。
是非観に行って頂きたい。 -
実演鑑賞
満足度★★★
チェーホフの原作を、アイルランドのブライアン・フリールが翻案した『ワーニャおじさん』。駅前劇場のステージ側にも客席を作り、横長のスペースを客席で挟み込む形。約140分。

 papamomo 老年団・サポート・センター(66)
papamomo 老年団・サポート・センター(66)
 ヴォンフルー(2419)
ヴォンフルー(2419)
 ピメ(235)
ピメ(235)
 しゅう(261)
しゅう(261)
 ハンダラ(10611)
ハンダラ(10611)
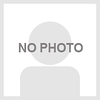 ベンジャミン2号(1243)
ベンジャミン2号(1243)
 ヴォンフルー(2419)
ヴォンフルー(2419)
 ベンジャミン2号(1243)
ベンジャミン2号(1243)