 公演情報
「雑種 小夜の月」の観てきた!クチコミ一覧
公演情報
「雑種 小夜の月」の観てきた!クチコミ一覧
-
実演鑑賞
満足度★★★★★
観劇前日,台風のためどこにも出かけられず,あやめ十八番さんのHPを見ていたら,お団子屋さんシリーズ二作目の『雑種 花月夜』が観劇三昧で無料視聴できることを知ったので,観劇予習として『雑種 花月夜』を視聴した上で,当日の観劇に臨んだ。人物の関係性や性格,状況の設定が頭に入っているので,最初から芝居の世界に引き込まれて,2時間の観劇時間,芝居にのめり込んでしまった。もう完璧!お見事!物語,演奏,舞台装置,役者さんの演技(設営等も含む。),細かいところも含めて素晴らしいの一言に尽きる。これは絶対おススメの舞台。観劇後,無性にお団子が食べたくなり,帰宅途中に購入したのは余談である。
-
実演鑑賞
満足度★★★★★
2回目。
台風直撃土砂降りの東京、散々な目に遭った。
Life is dream. Life is but a dream.
人生は夢、人生は夢に過ぎないよ。
この作品は一つの楽曲のように作り込まれている。そのセンスを高評価。岡本喜八や深作欣二には秘密があった。それはフィルムを編集する際、ジャズのリズムで細かくカットを繋ぐこと。テンポと気持ちよく刻んだ繋ぎに観客はノっていく。挟み込まれるメロディー、リフレイン、快楽原則。それは曲の構造そのもの。だがセンスは歳と共に落ちていく。黒澤明も卓越した反射神経でカットを繋いで大衆を熱狂させたが、やはり衰えていった。アカデミー名誉賞を受賞した時の有名なスピーチ。「私にはまだ“映画”というものがよく解っていない。」大家の謙遜のように捉えられたが、実は晩年に語っている。「最近、ちょっと見えてきたんだよね。“映画”はカットとカットの間に垣間見える。」
“映画”というものを一瞬だけでも見せる為のカットの連なり。
この作品の演出は一つの曲を構成する為のもの。話自体は定番の人情物かも知れない。かつて山田洋次は大ヒット作となった『男はつらいよ』を会社からシリーズ化するよう要求されて悩んでいた。おんなじ話を再生産していくことに果たして意味があるのか?作る方にとってもキツい。高名な落語家に相談したところ、「私は古典落語をやる時は来ているお客さんがそれを初めて聴くものだと思ってやっています。何度やったものでも初めてそれに触れるお客さんはいる。その人の為に新作としてやるのです。」
そこで何かを掴んだ山田洋次は『男はつらいよ』を続けることにした。
ゲストは活動弁士の片岡一郎氏。サイレント映画こそ映画の構造の真髄を知る機会。何が伝わって何が伝わらないのか。
佐原囃子(千葉県香取市、佐原の大祭の祭囃子)を演奏する囃子方を下座連(げざれん)と呼ぶ。
福圓(ふくえん)美里さんはちょっと見た目が若すぎると思っていたが今回細かく観て納得。配役にも演出家の意志を感じた。
小口ふみかさんの漫画的に誇張した表現は見事。中野亜美さんと共にジェスチャーが秀逸。
川田希さんの気の強い古風な女の啖呵、極妻だ。 -
実演鑑賞
満足度★★★★★
お団子屋さんの朝の作業の歌がすごく細かくてどのように作られていくのかが分かりやすかった。
お盆に彼岸と此岸の話が良く合っていて本当にほっこりさせてもらいました。 -
実演鑑賞
満足度★★★★★
鑑賞日2024/08/12 (月) 18:30
初めてのあやめ十八番で、初めての経験しました。
生演奏は言わずもがな。ハートフルが少し溢れて触れられそうな感じにすぐに心地よくなっちゃいます。他愛もない日々にドラマがゆるやかにクロスしていて、日常の表現力がすごいなと。
ここまでノンフィクションに距離が近くて、同じキャストで数年かけて公演が創られていてって他にあるんでしょうか。つむぎちゃんとかも含めてもはやドキュメンタリーの様な気もするし、雑種はまだまだ長く続いてほしいです。(雑種以外も気になりますが!)
人をちょっと好きになるし、団子が食べたくなる舞台でした。 -
実演鑑賞
満足度★★★★
小劇場には珍しい季節狙いの夏芝居かと思ったら、これは日本劇作家協会の推薦・夏芝居で、この劇団のシリーズ公演の第三作でもある。
地域では知られている神社の参道にある名物団子屋一家の三代にわたる人間模様ホームドラマだ。雑種の飼い猫まで噛んでいるのもご愛嬌。
作者(堀越涼)の三十歳代の実体験が下敷きになっている由で、今も地方都市に綿々と残っている日本の伝統的な命のつながりを、神社、その祭礼儀式、伝統信仰を護る家族の生き方、地域との関係の中で、いまに続く生活ドラマとして描いている。
たとえば、加藤拓也の「ドードーが落下する」が地方の演劇青年の人生を辛く切実に描いているのに比べると、こちらに登場する都会からやってきた演劇青年(当日客演・藤原祐規)はいかにもの今時のその場に生きる青年である。どちらがいいということではなく、どちらも今までの日本の地方に生きる人々の類型から逸脱していく時代の子である。青年だけではない、伝統の中に生きている老若の登場人物たちの生き方にも、時代の生き方は反映している。そこが、夏芝居のシリーズドラマを装ってこの夏枯れの時期に上演されたこの芝居の一番の見どころだろう。
使いにくい横に長い座高円寺の舞台を中央に置いて客席を対面に組んだ古典劇のような舞台はノーセット、上手に稲荷神社の鳥居、下手に五本の竹を立て、そこに西洋音楽の四人編成のバンド(木管のファゴットが入るというユニークな編成。V,Gu,Pf)を下座として置くという抽象舞台で、劇中歌もあり、邦楽楽器も活躍する。一見無秩序な構えなのだが、これが神社の門前町という舞台によく似あう。この美術・音楽が第一。物語は女性を軸にした三代のホームドラマなのだが。人情噺の相続劇に落ちそうなところを女性個人の生き方の問題にしているところが第二。三十歳を軸に観客が同感しながら見ているのは、都会に生きる人々も地方に根があるからであろう。客席は幕内も多いがそれだけでは230の席がみるみる埋まるということにはならない。
注文を言えば、キャラを出すことに慣れている花組の俳優(男優)たちに比べ女優陣の性格表現が弱い(面白くない)ところ、広い舞台を持て余し気味で、女優陣のセリフがお互いに届かず会話が単調になってしまったこと、音楽が意欲的なのはいいが過剰なこと(饒舌に通じる)。ほかの方々も指摘されているが脚本が説明過剰なこところ、ことに出だしと最後の部分、説明は演技で埋めなければ、シチュエーションドラマは締まらない。それは17名に猫という登場人物の数がこの芝居の構えとしては多すぎるところからきている。
作・演出も俳優も甘さは目につくが、それらはすべて、物語の日常のやさしさと道具立て、夏芝居の気分で帳尻を合わせてしまった2時間5分である。
せっかくタイトルにも使っている雑種の猫の使い方までは手が回らなかった。 -
実演鑑賞
良くも悪くも昔のホームドラマを見ているようだ。
演出も演技も素晴らしいのだがストーリーは田舎の日常そのものである。
私は演劇に非日常を求めているので合っていなかったというのが結論だ。 -
実演鑑賞
満足度★★★★★
鑑賞日2024/08/12 (月)
観てきました☆ まず劇場に入ったところから洗練された舞台美術と対面舞台に期待が高まります☆
あやめのお芝居は何度も観てきましたが、今回も素晴らしかったです☆ -
実演鑑賞
満足度★★★★★
いきなり偉そうな言い方になるが「上手くなったなァ・・」というのが最初に漏れた感想。お盆らしく御霊もご登場遊ばすが過剰に意識させず涙腺を弄られるあざとさがなく、それはつまり「リアル」そのものに語らせている。「いい話」には目が厳しくなる自分だが、過不足がない。千葉の田舎町を舞台に凡そ三世代にわたる家族と地域の半径幾許の中の物語が紡がれる。
「雑種」とは作者の実家の団子屋を舞台に書かれたシリーズとの事だが、それだけに作者の飾らぬ筆致が印象的である。(ノリの良い演出は健在だが、空隙を埋めるような過剰さ、つまり借りて来た感がないのはそういう事なんだろう。)物語の中心は母という事にはなるが、皆に等しく眼差しが注がれ、いずれ忘れ去られ、今もひっそりと健気に暮らす者たちの群像が浮かび上がる。どこにあってもおかしくない庶民の物語。
当地を訪問するお客が日替りゲストらしい。私は知らないが花組芝居の名物役者らしく(あやめの客層でもあるのだろう)一々笑いが起きていた。
座組を支える金子侑香の立ち回り方は長女という役柄をはみ出て気丈な女将の如くなのが(主役でなくとも)滲み出るが、客席を向いた時その目力を初めて認識。
音楽(効果も)の生演奏も相変わらず質が高い。祭り囃子を奏でる下座に太鼓までは判るが演者が篠笛まで吹いていた(二人も。リード付き篠笛なんてのがあれば習得に時間は要さないかも知れないが..聞こうと思って忘れた)。 -
実演鑑賞
満足度★★★★★
身につまされる観客も多かろう。何れの役者も自然体で良い演技をしているし、生演奏は無論のこと、照明も良いし、等身大の脚本、演出もグー。
-
実演鑑賞
満足度★★★★★
中盤から終盤にかけての怒涛の展開が好きでした
序盤は説明・導入が丁寧すぎるような気がしないでもないが、あのほんわかした展開が好きな人にはたまらないんだろうな
客席で挟まれたステージも端から端まで上手くて
利用していて素晴らしかった、観にくいと感じることが
なかったので良かった
シリーズものですが過去作を観ていなくても充分
楽しめますが、観劇三昧で2時間過去作を観て行ったほうが私はより楽しめました〜、おすすめです -
実演鑑賞
満足度★★★★★
とても素敵な作品でした。
お団子屋さんを舞台に、現在と過去を交錯させながら描いた物語で、リアル感があり観応えがありました。
優しい気持ちになると共に、亡くなった両親や、昔を思い出し、涙腺が緩みました。
役者さん達の演技も良いし、生演奏も良かったです。
大満足の舞台でした! -
実演鑑賞
満足度★★★★
面白い、お薦め。
日本の原風景、良き日本人を見るような公演。
本作は、劇団代表の堀越涼 氏の実家の団子屋をモデルにした雑種シリーズの第三作目。何処か分かるが当日パンフにも明記していないため、敢えて伏せておく。しかし その土地の方言で喋り、この時期に相応しい風習などを盛り込んだ家族劇。家制度や血縁とは といった一筋縄ではいかない問題や思惑を絡め、観客の心を揺さぶる。その情景は心温まるもの。
物語の肝は、<駆け落ち>と<化け猫>か。
この物語は 堀越氏の歩みを切ったり貼ったりしながら作った、人生に限りなく近い話だという。悪人は登場しない、しかし立場や考え方の違い、思惑によって小さな騒動が起きる。その山あり谷ありの人生(物語)は、多かれ少なかれ観客に寄り添い 共感を得ていると思う。課題や問題を乗り越えるには、人の思いやり優しさであると。その滋味をしっかり味わえる秀作。
(上演時間2時間 休憩なし)

 ポチ様様(2104)
ポチ様様(2104)
 alltime(144)
alltime(144)
 ヴォンフルー(2391)
ヴォンフルー(2391)
 さらさら(618)
さらさら(618)
 Fenegy(1523)
Fenegy(1523)
 夏草(11)
夏草(11)
 旗森(750)
旗森(750)
 まなぶう(1105)
まなぶう(1105)
 バート(7508)
バート(7508)
 uz(1354)
uz(1354)
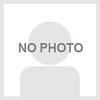 ゴージャス(1995)
ゴージャス(1995)
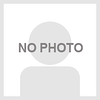 あおぞら(48)
あおぞら(48)
 ベンジャミン2号(1237)
ベンジャミン2号(1237)
 lattice(557)
lattice(557)
 ガチャピン(500)
ガチャピン(500)
 tottory(2602)
tottory(2602)
 ハンダラ(10585)
ハンダラ(10585)
 寿司猫(190)
寿司猫(190)
 こぴ(3876)
こぴ(3876)
 タッキー(4095)
タッキー(4095)